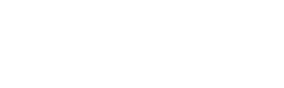Webサイトで商品購入やお問い合わせを獲得する際、最後の関門となるのが入力フォームです。せっかく興味を持ってくれたユーザーが、フォーム入力の途中で離脱してしまうケースは決して少なくありません。実際に、入力フォームの離脱率は平均70%以上とも言われており、多くの企業が機会損失に悩んでいます。このような課題を解決するのがEFO対策(Entry Form Optimization)です。EFO対策を適切に実施することで、ユーザビリティが向上し、コンバージョン率を大幅に改善できる可能性があります。本記事では、EFO対策の基本概念から具体的な施策まで、実践的な内容を体系的に解説していきます。
EFO対策の基本概念
EFO対策とは、Entry Form Optimization(エントリーフォーム最適化)の略称で、Webサイトの入力フォームを改善してユーザーの完了率を向上させる取り組みです。
EFO対策は、ユーザーがフォーム入力を開始してから完了するまでの過程において、離脱要因を特定し除去することを目的としています。具体的には、入力項目の最適化、エラー表示の改善、入力支援機能の実装などが含まれます。
EFO対策が重要な理由
現代のWebマーケティングにおいて、EFO対策の重要性はますます高まっています。ユーザーの行動分析によると、フォーム入力時の離脱要因として最も多いのが「入力項目が多すぎる」「エラーメッセージが分かりにくい」「入力方法が不明確」といった点です。
これらの問題を解決することで、既存の集客施策の効果を最大化できます。つまり、SEO対策や広告運用で獲得した貴重なトラフィックを、確実にコンバージョンに結び付けることができるのです。
従来のフォーム最適化との違い
EFO対策は、単なるデザインの改善ではなく、ユーザーの行動心理を深く理解した上で実施される包括的な最適化手法です。従来のフォーム改善が見た目の美しさや機能の追加に重点を置いていたのに対し、EFO対策はデータに基づいてユーザーの離脱ポイントを特定し、科学的なアプローチで改善を行います。
また、継続的な分析と改善を前提としており、一度の施策で終わるものではありません。ユーザーの行動データを定期的に分析し、PDCAサイクルを回しながら最適化を続けていくことが特徴です。

EFO対策は、ユーザーの立場に立って考えることが何より大切です。データ分析と改善を継続することで、必ず成果につながりますよ

入力フォーム離脱率の現状と問題点
入力フォームにおける離脱率の高さは、多くの企業が直面している深刻な課題です。一般的なECサイトでは、カート投入後から購入完了までの離脱率が約70%に達するという調査結果もあります。
この高い離脱率は、企業の売上機会の大幅な損失を意味しています。例えば、月間1,000人がフォームに到達している場合、離脱率を10%改善するだけで月間100人の新規顧客獲得につながる計算になります。
主な離脱要因の分析
フォーム離脱の主な要因として、以下の点が挙げられます。まず、入力項目の多さが最も大きな要因とされています。ユーザーは時間をかけて入力することに対して心理的な負担を感じるため、項目数が増えるほど離脱率も高くなる傾向があります。
| 離脱要因 | 発生頻度 | 改善難易度 |
|---|---|---|
| 入力項目が多い | 高 | 中 |
| エラーメッセージが不明確 | 高 | 低 |
| 入力形式が分からない | 中 | 低 |
| セキュリティへの不安 | 中 | 高 |
| 読み込み速度が遅い | 低 | 中 |
エラーメッセージの不明確さも重要な離脱要因の一つです。「入力内容に誤りがあります」といった曖昧なメッセージでは、ユーザーは具体的に何を修正すべきかが分からず、結果として離脱してしまいます。
業界別の離脱率傾向
業界によってフォーム離脱率には大きな差があります。BtoB企業のお問い合わせフォームでは比較的離脱率が低い傾向にある一方、ECサイトの決済フォームでは離脱率が高くなる傾向があります。
これは、ユーザーの購買意欲の強さや、入力する情報の機密性、フォーム完了までのプロセスの複雑さなどが影響していると考えられます。業界特性を理解した上でEFO対策を実施することが重要です。
離脱タイミングの特定方法
ユーザーがどの段階で離脱するかを正確に把握することが、効果的なEFO対策の第一歩となります。Googleアナリティクスのファネル分析や、ヒートマップツールを活用することで、離脱が多発するポイントを特定できます。
特に注目すべきは、必須項目への入力開始時点と、エラー発生時点での離脱率です。これらのデータを定期的に分析し、問題のある箇所を優先的に改善していくことが効果的です。

離脱率の高さは確かに問題ですが、改善の余地が大きいということでもありますね。データを活用して着実に改善していきましょう
バクヤスAI 記事代行では、無料でLLMO診断を実施中です。

効果的なEFO対策の7つの実践施策
EFO対策を成功させるためには、体系的なアプローチが必要です。以下では、実際に効果が確認されている7つの実践的施策について詳しく解説します。
これらの施策は、ユーザビリティの向上とコンバージョン率の改善を同時に実現できる手法として、多くの企業で導入が進んでいます。
入力項目の最適化と削減
フォームの入力項目数は、離脱率に最も大きな影響を与える要素の一つです。項目数が1つ増えるごとに離脱率が約7%上昇するという調査結果もあり、不要な項目の削除は最優先で取り組むべき施策です。
入力項目の最適化では、「本当に必要な情報か」「後から取得できる情報ではないか」という観点で各項目を見直すことが重要です。例えば、お問い合わせフォームにおいて、会社の業界や従業員数などの情報は、後日の商談で確認しても問題ないケースが多いでしょう。
入力項目削減のチェックポイント
- 必須項目は5個以下に抑制する
- 任意項目は目的を明確にする
- 同じ情報を複数回入力させない
- 自動取得できる情報は手入力を避ける
エラーメッセージの改善
分かりやすいエラーメッセージは、ユーザーがフォーム入力を完了するために不可欠な要素です。「入力内容にエラーがあります」といった曖昧なメッセージではなく、具体的な修正方法を示すことが重要です。
リアルタイムバリデーション機能を実装することで、ユーザーが入力を完了した瞬間にエラーの有無を確認できるため、修正がより容易になります。
| 悪い例 | 良い例 | 改善ポイント |
|---|---|---|
| 入力内容にエラーがあります | メールアドレスの形式が正しくありません | 具体的な問題点を明示 |
| 必須項目です | お名前をご入力ください | 何を入力すべきかを明確化 |
| 文字数が足りません | 8文字以上で入力してください | 具体的な条件を提示 |
入力支援機能の実装
入力支援機能の実装により、ユーザーの負担を大幅に軽減できます。代表的な機能として、郵便番号から住所の自動入力、ふりがなの自動生成、入力形式のガイド表示などがあります。
特に、住所入力の自動化は効果が高く、離脱率を20%以上改善できるケースもあります。また、クレジットカード番号の自動フォーマット機能なども、ユーザビリティ向上に大きく貢献します。
プログレスバーの設置
複数ステップにわたるフォームでは、プログレスバーの設置が離脱防止に効果的です。現在の進捗状況と残りのステップ数を可視化することで、ユーザーの完了意欲を維持できます。
プログレスバーは、単純な数値表示よりも視覚的な表現の方が効果的とされています。また、「あと2分で完了」といった時間の目安を併記することで、さらなる効果が期待できます。

これらの施策は組み合わせることで相乗効果を生み出します。段階的に導入して効果を測定していくのがおすすめです
バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!
バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。
ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様
生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。
親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。
▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

EFO対策の効果測定方法
EFO対策の成果を正確に把握するためには、適切な指標設定と継続的な測定が不可欠です。単純にコンバージョン率の向上を見るだけでなく、ユーザーの行動変化を多角的に分析する必要があります。
効果測定では、定量的な指標と定性的な指標の両方を組み合わせることで、より精度の高い改善施策の立案が可能になります。
重要なKPI指標の設定
EFO対策における主要なKPI指標として、フォーム到達率、入力開始率、各ステップでの離脱率、フォーム完了率などがあります。これらの指標を組み合わせることで、問題のあるポイントを特定できます。
特に重要なのは、入力開始率とフォーム完了率の差分です。この数値が大きいほど、フォーム内での離脱が多発していることを意味します。
| 指標名 | 計算方法 | 改善目標 |
|---|---|---|
| フォーム到達率 | フォーム到達数/総セッション数 | 5%以上 |
| 入力開始率 | 入力開始数/フォーム到達数 | 70%以上 |
| フォーム完了率 | 完了数/入力開始数 | 60%以上 |
| 総合コンバージョン率 | 完了数/フォーム到達数 | 25%以上 |
分析ツールの活用方法
Googleアナリティクスの目標設定機能を使用して、フォームの各ステップでのコンバージョンを追跡できます。さらに、ヒートマップツールを併用することで、ユーザーがフォーム上のどこをクリックし、どこで躊躇しているかを視覚的に把握できます。
A/Bテストツールを活用することで、異なるフォーム設計の効果を定量的に比較検討できます。例えば、入力項目の順番を変更した場合の効果や、エラーメッセージの文言変更による影響を測定できます。
改善サイクルの構築
EFO対策は一度実施すれば完了というものではなく、継続的な改善が必要です。月次での効果測定と四半期での大幅な見直しを組み合わせることで、持続的な成果向上が期待できます。
改善サイクルでは、仮説立案、施策実施、効果測定、次の改善案検討というPDCAサイクルを回していきます。小さな変更でも継続的に実施することで、大きな成果につながる場合が多くあります。
効果測定の実施チェックリスト
- ベースライン数値の記録完了
- 測定期間の設定完了
- A/Bテスト環境の構築完了
- 定期的なレポート作成体制の確立
- 改善案の優先順位付け完了

EFO対策成功のための継続的改善
EFO対策で持続的な成果を上げるためには、一時的な施策実施だけでなく、組織的な取り組みと継続的な改善体制の構築が重要です。ユーザーの行動パターンや市場環境の変化に応じて、柔軟に対応していく姿勢が求められます。
成功企業の多くは、EFO対策を単発のプロジェクトとしてではなく、継続的な業務プロセスとして組織に根付かせています。
組織体制の整備
EFO対策を成功させるためには、明確な責任者の設置と関係部署間の連携体制が不可欠です。マーケティング部門、開発部門、顧客サポート部門が連携して取り組むことで、より効果的な改善が実現できます。
特に重要なのは、ユーザーからの直接的なフィードバックを収集・分析する仕組みの構築です。顧客サポート部門に寄せられる問い合わせ内容は、フォーム改善の重要なヒントとなります。
ユーザーフィードバックの活用
定量データだけでなく、ユーザーの生の声を収集することで、数値では見えない問題点を発見できます。フォーム完了後のアンケート実施や、カスタマーサポートへの問い合わせ分析などが有効です。
また、ユーザビリティテストを定期的に実施することで、実際のユーザー行動を観察し、想定とは異なる使用パターンを発見できる場合があります。
技術的な改善環境の整備
迅速な改善実施のためには、開発環境の整備も重要な要素です。A/Bテストの実施体制、効果測定ツールの導入、改善内容の迅速なデプロイ体制などが整っていることで、施策の効果を最大化できます。
特に、フォーム周りの技術的な制約が改善の妨げとならないよう、柔軟性のあるシステム設計を心がけることが重要です。
| 改善フェーズ | 実施頻度 | 主な活動内容 |
|---|---|---|
| 日次モニタリング | 毎日 | コンバージョン数・離脱率の確認 |
| 週次分析 | 毎週 | 詳細データ分析・問題点抽出 |
| 月次改善 | 毎月 | 小規模改善施策の実施 |
| 四半期見直し | 3ヶ月毎 | 大幅な設計変更・戦略見直し |
よくある質問
EFO対策に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。実際の導入時に参考にしていただければと思います。
- EFO対策の効果が現れるまでにどの程度の期間が必要ですか?
-
一般的には、施策実施後2〜4週間程度で初期効果を確認できるケースが多いです。ただし、統計的に有意な結果を得るためには、最低でも1〜2ヶ月間のデータ蓄積が必要です。大幅な改善効果を実感するためには、3〜6ヶ月程度の継続的な取り組みが推奨されます。
- EFO対策に必要な予算の目安はどの程度でしょうか?
-
予算は実施する施策の規模によって大きく異なりますが、基本的なEFO対策であれば月額10万円程度から始めることができます。専用ツールの導入が必要な場合は月額5〜20万円程度、大規模なシステム改修を伴う場合は数百万円の初期投資が必要になる場合もあります。ROIを考慮すると、多くの企業で投資に見合った効果が得られています。
- BtoB企業とBtoC企業でEFO対策の内容は異なりますか?
-
基本的な考え方は同じですが、ユーザーの行動特性に違いがあるため、重点を置く施策が異なります。BtoB企業では信頼性やセキュリティに関する表示が重要である一方、BtoC企業では入力の簡便性や決済方法の多様性が重視される傾向があります。業界特性を理解した上で、適切な施策を選択することが重要です。
- スマートフォン対応のEFO対策で特に注意すべき点はありますか?
-
スマートフォンでは画面サイズの制約があるため、1画面に表示する項目数を最小限に抑えることが重要です。また、タッチ操作に適したボタンサイズの確保、ソフトウェアキーボードとの干渉防止、入力項目のフォーカス時の画面スクロール対応などが必要です。特に、電話番号やメールアドレスなどの入力では、適切なキーボード表示の設定も重要な要素となります。
これらの質問以外にも、EFO対策に関する疑問がございましたら、専門のコンサルタントにご相談いただくことをお勧めします。
まとめ
EFO対策は、Webサイトのコンバージョン率向上において極めて重要な施策です。入力フォームの離脱率を改善することで、既存の集客施策の効果を最大化し、ROIの向上を実現できます。
成功の鍵は、ユーザーの行動データに基づいた科学的なアプローチと、継続的な改善サイクルの構築にあります。入力項目の最適化、エラーメッセージの改善、入力支援機能の実装など、7つの実践的施策を段階的に導入することで、着実な成果を上げることができます。
EFO対策は一度の施策で完結するものではなく、ユーザーの行動変化や技術進歩に応じて継続的に改善していく必要があります。組織的な取り組み体制を整備し、データに基づいた意思決定を行うことで、持続的な成果向上が期待できるでしょう。