WebサイトのSEO対策において、直帰率は重要な指標の一つです。直帰率が高いということは、訪問者がサイトに満足していない可能性があり、検索エンジンからの評価にも影響を与える可能性があります。しかし、直帰率の正確な意味や離脱率との違いを理解している方は意外と少ないのが現状です。
本記事では、直帰率の基本概念から離脱率との明確な違い、そしてSEOへの影響について詳しく解説します。さらに、直帰率を改善するための具体的な方法やベストプラクティスまで、包括的にご紹介していきます。Webサイトのパフォーマンスを向上させ、より多くのユーザーにとって価値のあるサイト作りを目指すための知識を身につけましょう。

直帰率の基本知識
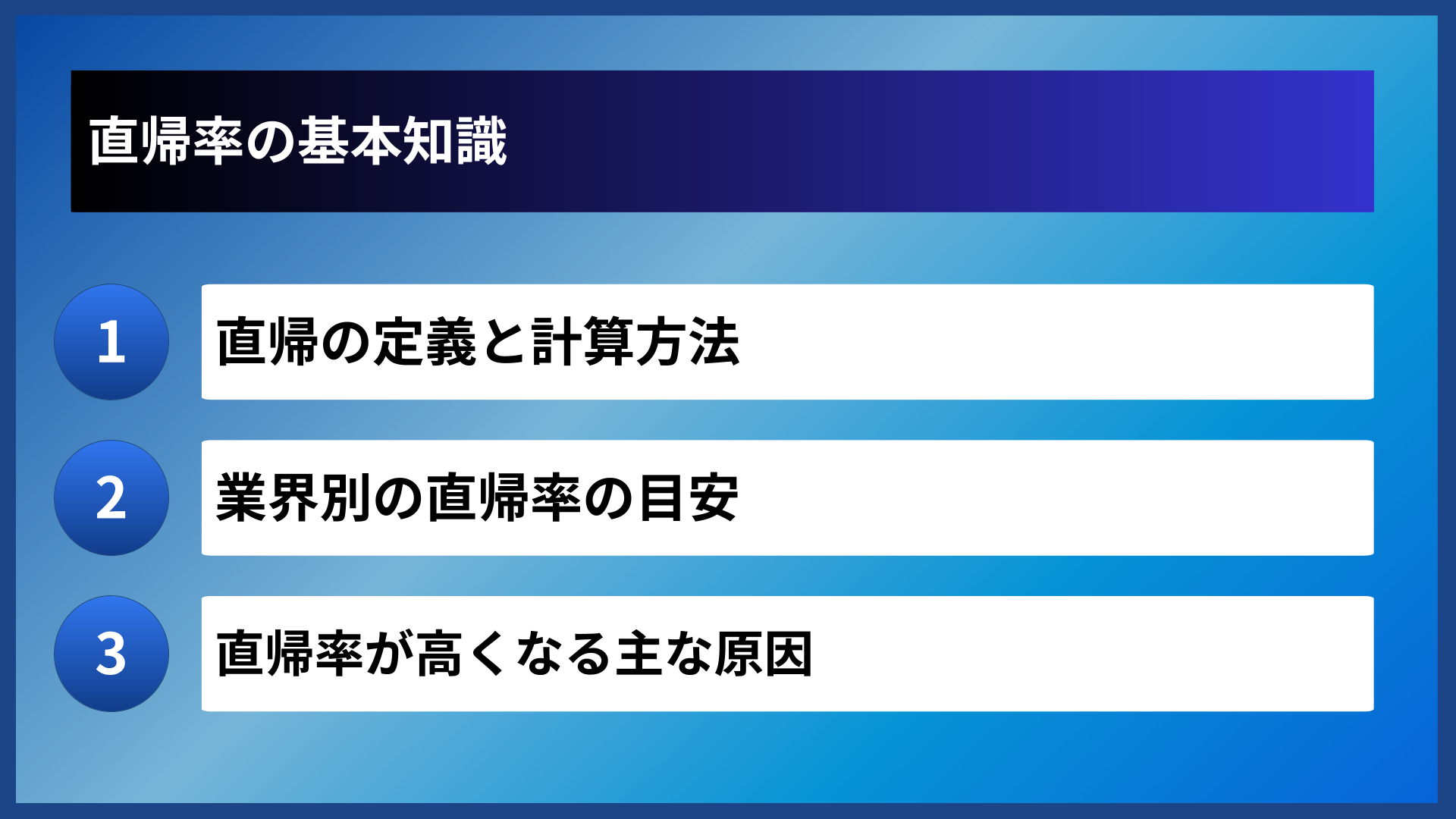
直帰の定義と計算方法
直帰の定義は非常にシンプルです。ユーザーがWebサイトに訪問し、最初のページのみを閲覧してサイトを離れた場合、それが「直帰」とみなされますこの際、ページの閲覧時間の長さは関係ありません。
直帰率の計算式は以下の通りです。
| 計算要素 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 直帰したセッション数 | 1ページのみ閲覧して離脱したセッション | 300セッション |
| 総セッション数 | サイト全体の総訪問数 | 500セッション |
| 直帰率 | 直帰セッション数 ÷ 総セッション数 × 100 | 60% |
この計算により、サイト全体または特定のページの直帰率を正確に把握することができます。
業界別の直帰率の目安
直帰率は業界や業種によって大きく異なります。一般的に、情報提供型のサイトでは直帰率が高くなりやすく、ECサイトでは低くなる傾向があります。
| 業界・サイト種別 | 平均直帰率 | 特徴 |
|---|---|---|
| ニュース・メディアサイト | 60%〜80% | 記事を読んで満足し離脱するため高め� |
| ECサイト | 30%〜50% | 商品閲覧や購入手続きで複数ページを回遊 |
| 企業サイト | 40%〜60% | 会社情報や製品詳細を複数ページで確認 |
| ブログ | 50%〜70% | 記事の内容により大きく変動 |
これらの目安を参考に、自社のサイトが属する業界の平均値と比較することで、改善の必要性を判断できます。
直帰率が高くなる主な原因
直帰率が高くなる原因は多岐にわたります。まずは、ページの読み込み速度が遅いことが挙げられます。ユーザーは3秒以上ページの読み込みを待つことを嫌う傾向があり、表示が遅いとすぐに離脱してしまいます
また、コンテンツの品質も重要な要因です。検索クエリとページの内容が一致していない場合や、情報が古い・不正確である場合も直帰率上昇の原因となります。さらに、モバイルデバイスでの表示が最適化されていない場合も、現在のユーザー行動を考慮すると大きな問題となります。
直帰率チェックポイント
- ページの読み込み速度は3秒以内か
- 検索クエリとコンテンツ内容は一致しているか
- モバイルでの表示は最適化されているか
- ナビゲーションは分かりやすいか
- 関連コンテンツへの導線は設置されているか

直帰率の基本を理解したところで、次は離脱率との違いを把握して、より正確な分析ができるようになりましょう。

直帰率と離脱率の違い
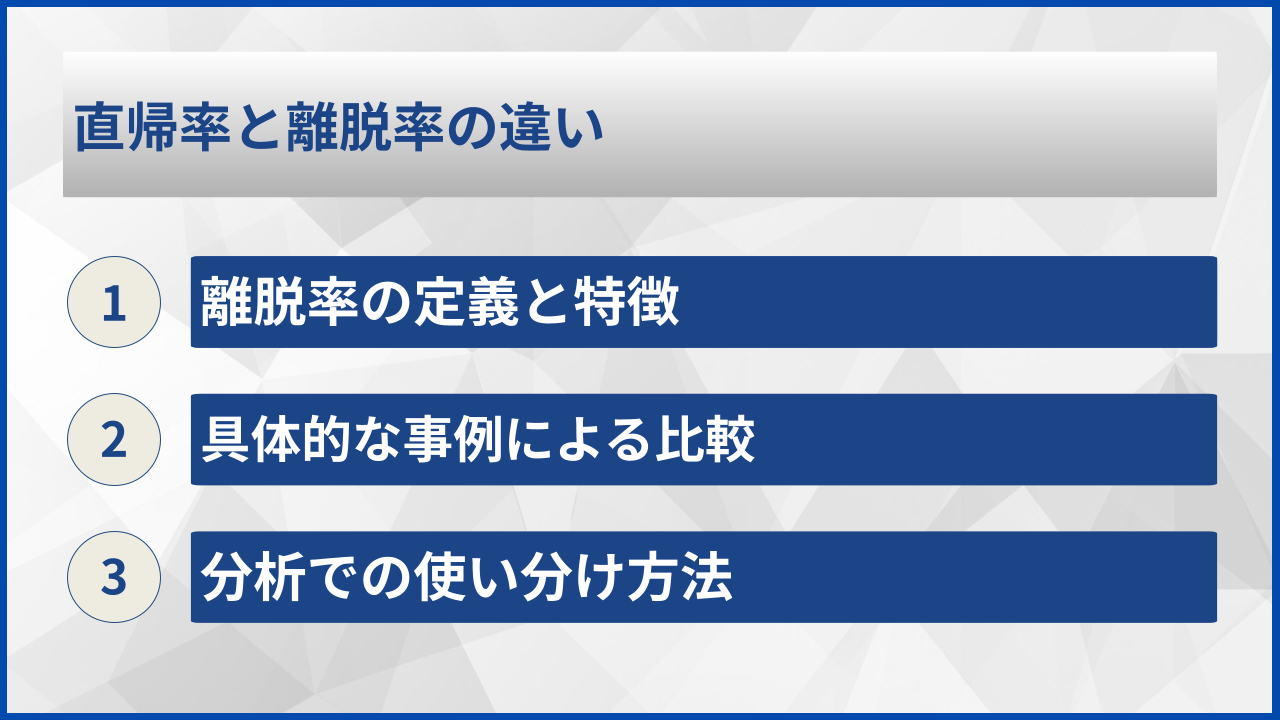
離脱率の定義と特徴
離脱率は、そのページでユーザーのセッションが終了した割合を示します。離脱率が高いページは、ユーザーにとって最終的な目的を達成するページである可能性が高く、必ずしも悪い指標ではありません
例えば、ECサイトの購入完了ページやお問い合わせ完了ページなどは、離脱率が高くても問題ありません。むしろ、これらのページでの離脱は成功を意味する場合が多いのです。
| 指標 | 定義 | 計算基準 |
|---|---|---|
| 直帰率 | 1ページのみ閲覧して離脱 | そのページから始まったセッション |
| 離脱率 | そのページで最後に離脱 | そのページを閲覧した全セッション |
具体的な事例による比較
具体的な事例を使って、直帰率と離脱率の違いを説明します。あるWebサイトの1日のアクセス状況を見てみましょう。
ユーザーAは「トップページ → 商品ページ → 購入ページ」の順で回遊し、購入ページで離脱しました。ユーザーBは「商品ページ」のみを閲覧してサイトを離脱しました。この場合、商品ページの直帰率と離脱率は以下のように計算されます。
| ユーザー | 閲覧経路 | 商品ページでの分類 |
|---|---|---|
| ユーザーA | トップ → 商品 → 購入 | 離脱なし(通過) |
| ユーザーB | 商品のみ | 直帰かつ離脱 |
| ユーザーC | 商品 → トップ → 離脱 | 直帰なし、離脱なし |
この事例では、商品ページの直帰率は約33%(3人中1人が直帰)、離脱率は約33%(3人中1人が商品ページで離脱)となります。
分析での使い分け方法
直帰率と離脱率は、それぞれ異なる分析目的で使用します。直帰率はランディングページの魅力度や初回訪問時のユーザー体験を測る指標として活用し、離脱率は各ページの役割達成度やユーザーフローの最適化に活用します
直帰率が高いページは、コンテンツの改善やナビゲーションの見直しが必要かもしれません。一方、離脱率が高いページは、そのページがユーザーの目的を達成させているか、適切な次のアクションへの導線があるかを確認する必要があります。
指標の使い分けチェックリスト
- 直帰率:ランディングページの初回印象を評価
- 直帰率:コンテンツの魅力度を測定
- 離脱率:各ページの役割達成度を確認
- 離脱率:ユーザーフローの最適化に活用
- 両方:総合的なサイト改善の指標として併用

この2つの違いを理解すると、サイト分析の精度が格段に向上します。次は、これらがSEOに与える影響について見ていきましょう。
バクヤスAI 記事代行では、
高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

SEOへの直帰率の影響
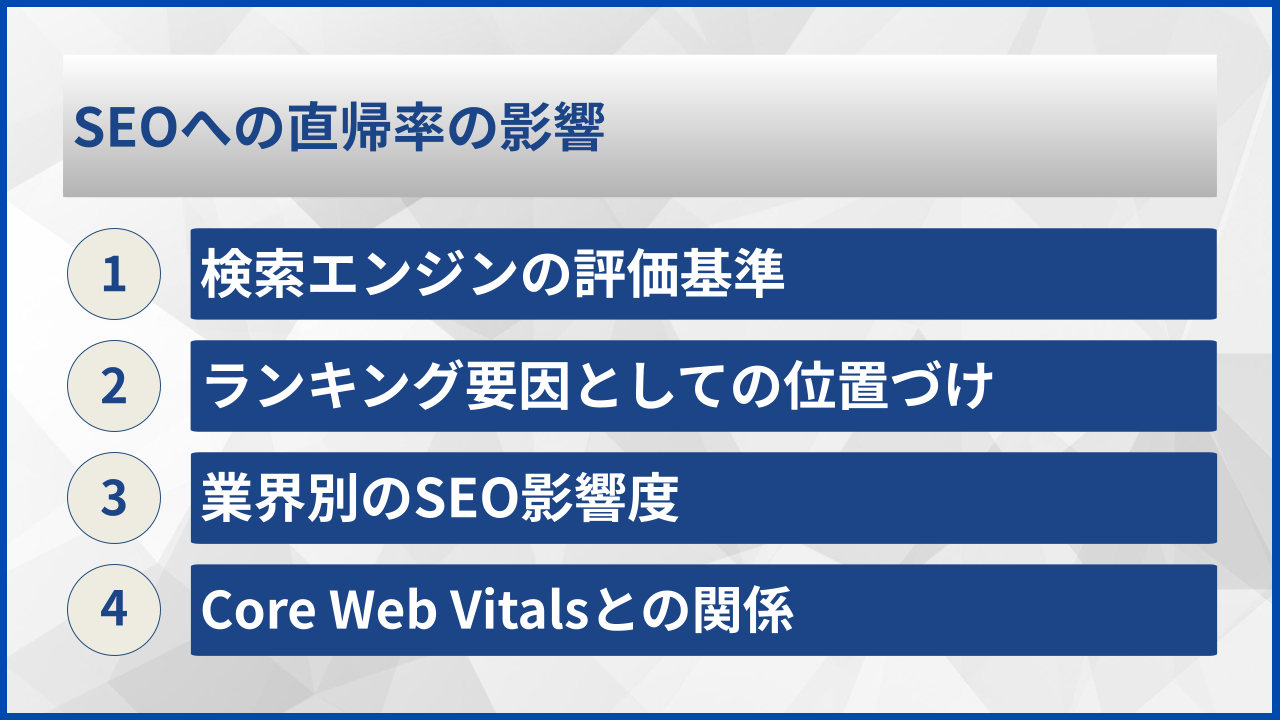
検索エンジンの評価基準
検索エンジンは、ユーザーが満足するコンテンツを上位表示することを目指しています。直帰率が極端に高いページは、ユーザーのニーズを満たしていない可能性があり、検索結果での順位に間接的な影響を与える可能性があります
Google が重視するユーザー体験の指標には、以下のようなものがあります。これらの指標は直帰率とも密接に関連しており、相互に影響し合っています。
| 評価指標 | 直帰率との関連 | SEOへの影響 |
|---|---|---|
| ページ読み込み速度 | 遅いと直帰率上昇 | Core Web Vitalsに直接影響 |
| モバイル最適化 | 未対応で直帰率上昇 | モバイルファーストインデックス対応 |
| コンテンツ品質 | 低品質で直帰率上昇 | E-A-T評価に影響 |
| ユーザビリティ | 悪いと直帰率上昇 | ユーザーエクスペリエンス評価 |
ランキング要因としての位置づけ
直帰率自体は明確なランキング要因として公表されていませんが、関連する要素は確実にSEOに影響を与えています。特に、ユーザーエンゲージメントの観点から、直帰率は重要な指標として位置づけられています。
滞在時間、ページビュー数、リピート訪問率などと合わせて、直帰率はサイト全体の品質を示すシグナルとして機能します。これらの指標が総合的に良好な場合、検索エンジンはそのサイトを高品質なサイトとして評価する傾向があります
業界別のSEO影響度
直帰率のSEOへの影響は、業界やサイトの性質によって異なります。情報提供型のサイトでは、ユーザーが求める情報を素早く見つけられることが重要で、適度な直帰率は必ずしも悪いものではありません。
一方、ECサイトやサービスサイトでは、複数ページの回遊が期待されるため、高い直帰率は改善が必要な指標となります。業界の特性を理解した上で、適切な目標値を設定することが重要です。
Core Web Vitalsとの関係
Google のCore Web Vitalsは、ユーザーエクスペリエンスを測る重要な指標群です。これらの指標が悪化すると直帰率も上昇する傾向があり、結果的にSEOにも悪影響を与える可能性があります
特に、LCP(Largest Contentful Paint)が遅い場合や、CLS(Cumulative Layout Shift)が発生する場合、ユーザーはページに対して不満を感じ、すぐに離脱してしまう可能性が高くなります。これらの技術的な要素と直帰率は密接に関連しているため、総合的な改善が必要です。

SEOと直帰率の関係性を理解できましたね。それでは、実際に直帰率を改善するための具体的な方法を学んでいきましょう!
バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!
バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。
ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。
サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様
生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。
親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。
▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

直帰率改善の具体的方法
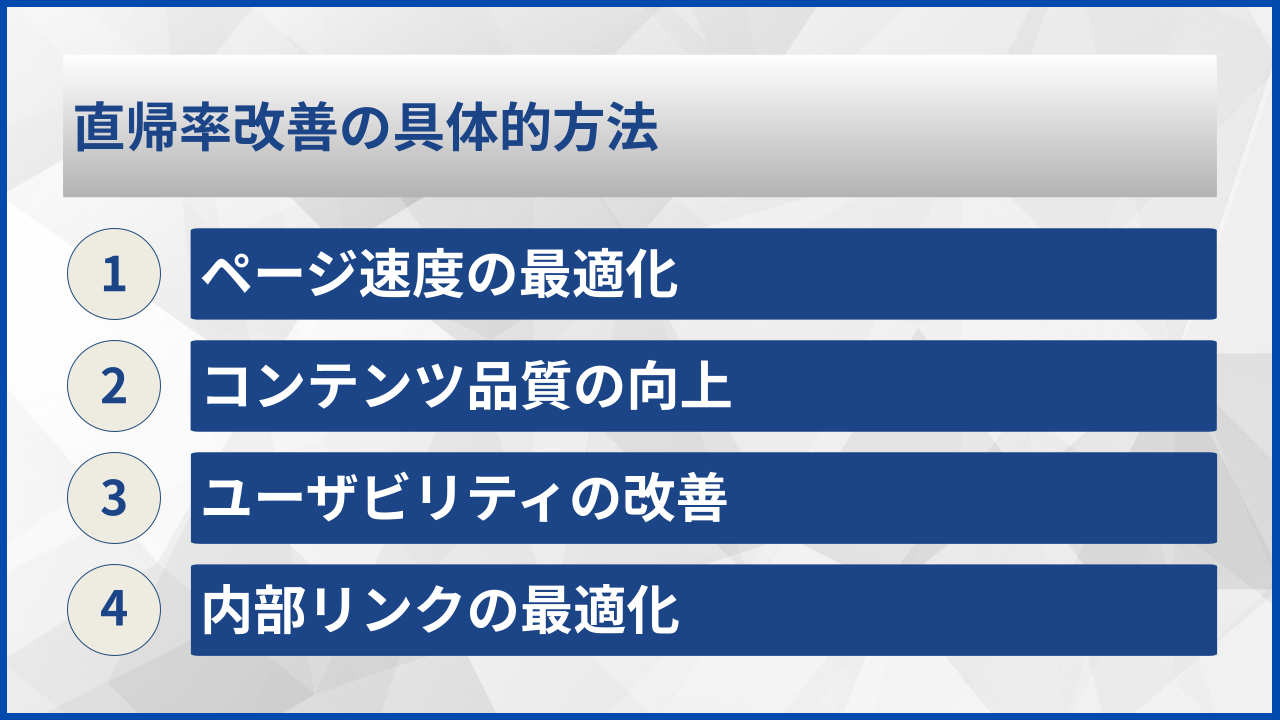
ページ速度の最適化
ページの読み込み速度は、直帰率に最も直接的な影響を与える要素の一つです。3秒以内にページが表示されない場合、約50%のユーザーが離脱してしまうというデータもありますこのため、速度改善は最優先で取り組むべき課題です。
具体的な速度改善方法には、以下のような施策があります。画像の最適化では、WebP形式の採用や適切な圧縮率の設定により、画質を保ちながらファイルサイズを大幅に削減できます。また、CDNの導入により、世界中のユーザーに対して高速なコンテンツ配信が可能になります。
| 改善項目 | 具体的施策 | 期待効果 |
|---|---|---|
| 画像最適化 | WebP形式、圧縮、遅延読み込み | 読み込み時間50%短縮 |
| キャッシュ活用 | ブラウザキャッシュ、CDN導入 | リピート訪問時の高速化 |
| コード最適化 | CSS/JS圧縮、不要コード除去 | データ転送量削減 |
| サーバー改善 | 高性能サーバー、HTTP/2対応 | 全体的なレスポンス向上 |
コンテンツ品質の向上
高品質なコンテンツは、ユーザーの関心を引きつけ、サイト内での滞在時間を延ばします。検索クエリとページ内容の一致度を高めることで、ユーザーの期待に応えるコンテンツを提供することができます
コンテンツ改善では、まず検索意図の正確な把握が重要です。ユーザーがどのような情報を求めてサイトに訪問したのかを理解し、それに対する明確で有用な回答を提供する必要があります。また、情報の鮮度も重要で、定期的な更新により常に最新の情報を提供することが求められます。
ユーザビリティの改善
使いやすいサイト設計は、ユーザーの満足度を高め、直帰率の改善に直結します。ナビゲーションの分かりやすさ、モバイル対応、レスポンシブデザインなど、多くの要素が関わってきます。
特に、ファーストビューの改善は重要です。ユーザーがページにアクセスした最初の数秒で、そのページの価値を判断するため、重要な情報を上部に配置し、次のアクションへの明確な導線を設置することが効果的です。
内部リンクの最適化
適切な内部リンクの設置は、ユーザーの回遊性を高め、直帰率の改善に大きく貢献します。関連性の高いコンテンツへのリンクを自然な形で配置することで、ユーザーの興味を継続させ、サイト内での滞在時間を延ばすことができます
内部リンクの最適化では、リンクテキストの選択も重要です。「詳細はこちら」のような曖昧な表現ではなく、リンク先の内容を明確に示すテキストを使用することで、ユーザーのクリック率を向上させることができます。
直帰率改善の実施チェックリスト
- ページ速度が3秒以内に最適化されているか
- コンテンツは検索意図と一致しているか
- モバイルでの表示が適切に最適化されているか
- ナビゲーションは直感的で分かりやすいか
- 関連コンテンツへの内部リンクが設置されているか
- ファーストビューで価値が伝わっているか

測定と分析方法
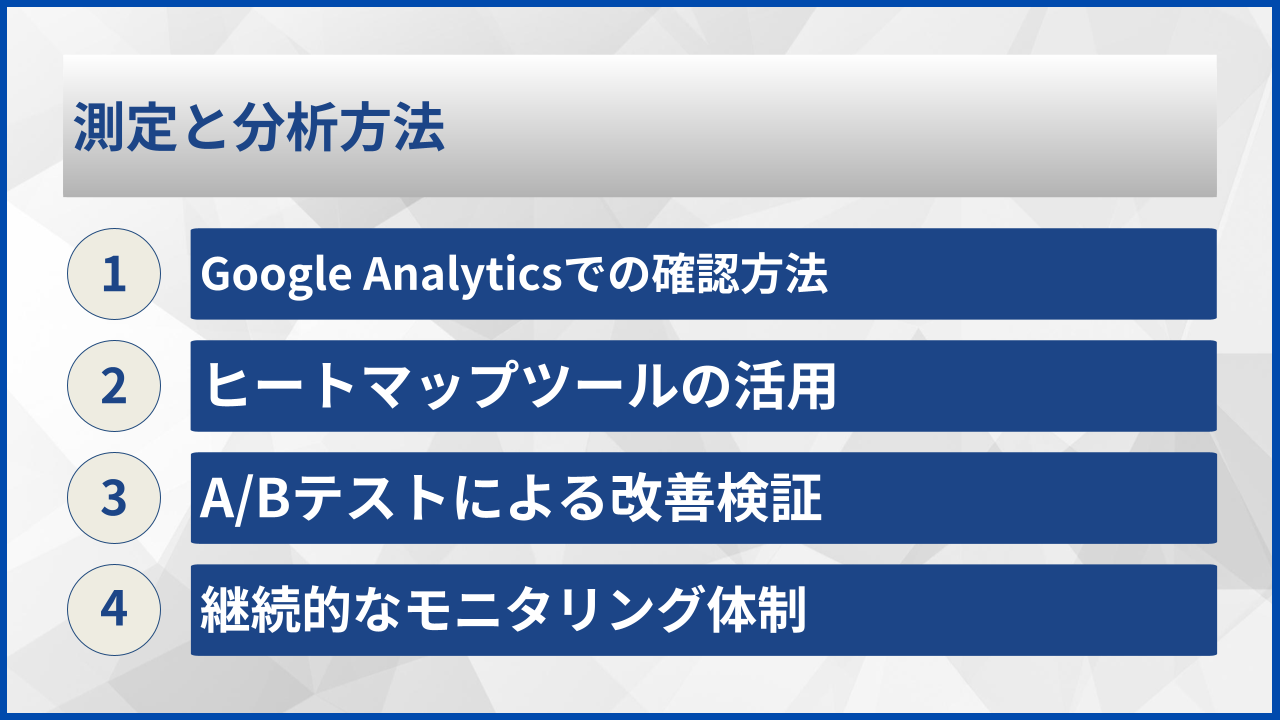
Google Analyticsでの確認方法
Google Analyticsは、直帰率分析において最も基本的で重要なツールです。レポート画面では、サイト全体の直帰率だけでなく、ページ別、流入元別、デバイス別の詳細な分析が可能です
具体的な確認方法として、「行動」→「サイトコンテンツ」→「すべてのページ」で各ページの直帰率を確認できます。また、「集客」→「すべてのトラフィック」→「チャネル」では、流入経路別の直帰率を分析することができ、どのチャネルからの訪問者の満足度が低いかを把握できます。
| 分析項目 | 確認方法 | 活用ポイント |
|---|---|---|
| ページ別直帰率 | 行動 → サイトコンテンツ → すべてのページ | 問題のあるページを特定 |
| 流入元別直帰率 | 集客 → すべてのトラフィック → チャネル | 流入経路の品質評価 |
| デバイス別直帰率 | ユーザー → モバイル → 概要 | デバイス最適化の評価 |
| 時系列変化 | 期間比較機能を活用 | 改善施策の効果測定 |
ヒートマップツールの活用
ヒートマップツールは、ユーザーがページ上でどのような行動を取っているかを視覚的に理解するために有効です。クリック位置、スクロール深度、マウスの動きなどを分析することで、直帰の原因をより具体的に特定できます。
特に、スクロールヒートマップでは、ユーザーがどこまでページを閲覧しているかが分かります。多くのユーザーがページの上部で離脱している場合、ファーストビューの改善が直帰率向上の鍵となります
A/Bテストによる改善検証
A/Bテストは、直帰率改善施策の効果を科学的に検証する方法です。異なるバージョンのページを同時に運用し、どちらがより良い結果を生むかを統計的に判断することができます。
テスト対象としては、ヘッドライン、画像、CTA(Call To Action)ボタンの配置、色使いなど、様々な要素が考えられます。一度に多くの要素を変更するのではなく、一つずつテストすることで、何が効果的だったのかを明確に把握できます。
継続的なモニタリング体制
直帰率の改善は一度実施すれば終わりではなく、継続的なモニタリングが必要です。定期的なレポート作成とレビューミーティングを実施することで、サイトの健康状態を常に把握し、必要に応じて迅速な対策を講じることができます
モニタリング体制では、アラート機能の設定も有効です。直帰率が一定の閾値を超えた場合に自動的に通知される仕組みを構築することで、問題の早期発見と対応が可能になります。
分析・測定のポイントチェックリスト
- Google Analyticsで定期的にデータを確認しているか
- ページ別・流入元別の詳細分析を実施しているか
- ヒートマップで具体的な行動パターンを把握しているか
- A/Bテストで改善施策の効果を検証しているか
- 継続的なモニタリング体制が構築されているか

データに基づいた分析と継続的な改善サイクルを回すことで、確実に直帰率を向上させることができますよ。
よくある質問
直帰率に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。これらの疑問を解消することで、より効果的な直帰率改善に取り組むことができるでしょう。
- 直帰率はどのくらいが適正ですか?
-
直帰率の適正値は業界やサイトの性質によって大きく異なります。一般的に、ニュースサイトやブログでは60%〜80%、ECサイトでは30%〜50%、企業サイトでは40%〜60%程度が平均的とされています。重要なのは、同業他社との比較や過去の自社データとの比較で改善傾向にあるかどうかです。
- 直帰率が低すぎる場合も問題ですか?
-
直帰率が極端に低い場合(10%以下など)は、Google Analyticsの設定に問題がある可能性があります。重複するトラッキングコードの設置や、自動的なページ遷移が発生している場合などが考えられます。また、意図的でない複数のイベント発火により、正確な直帰率が測定できていない可能性もあるため、設定を確認することをお勧めします。
- モバイルとPCで直帰率に大きな差がある場合の対処法は?
-
モバイルとPCで直帰率に大きな差がある場合、モバイル最適化に問題がある可能性が高いです。レスポンシブデザインの確認、タップしやすいボタンサイズの調整、モバイルでの読み込み速度改善、縦向きでの読みやすさの向上などを検討してください。現在は多くのユーザーがモバイルでアクセスするため、モバイル体験の向上は特に重要です。
- 直帰率改善の効果が出るまでにはどのくらいの期間が必要ですか?
-
直帰率改善の効果が現れる期間は、実施する施策の種類や規模によって異なります。ページ速度の改善やレイアウトの調整などの技術的な改善は、実施後1〜2週間程度で効果が見られることが多いです。一方、コンテンツの質的改善やSEO効果については、1〜3ヶ月程度の期間を要する場合があります。継続的な測定と分析を行いながら、長期的な視点で取り組むことが重要です。
これらの質問と回答を参考に、自社のサイト状況に応じた適切な改善策を検討してください。
まとめ
直帰率は、Webサイトの成果向上とSEO対策において重要な指標です。本記事では、直帰率の基本概念から離脱率との違い、SEOへの影響、そして具体的な改善方法まで包括的に解説いたしました。
直帰率の改善には、ページ速度の最適化、コンテンツ品質の向上、ユーザビリティの改善など、多角的なアプローチが必要です。また、Google Analyticsやヒートマップツールを活用した継続的な分析により、データに基づいた効果的な施策を実施することが成功の鍵となります。
重要なのは、業界特性を理解した適切な目標設定と、ユーザー視点に立った改善施策の実施です。一度の改善で終わらせるのではなく、継続的なモニタリングと改善サイクルを構築することで、長期的に安定したサイト運営が可能になります。ぜひ本記事の内容を参考に、自社サイトの直帰率改善に取り組んでください。



