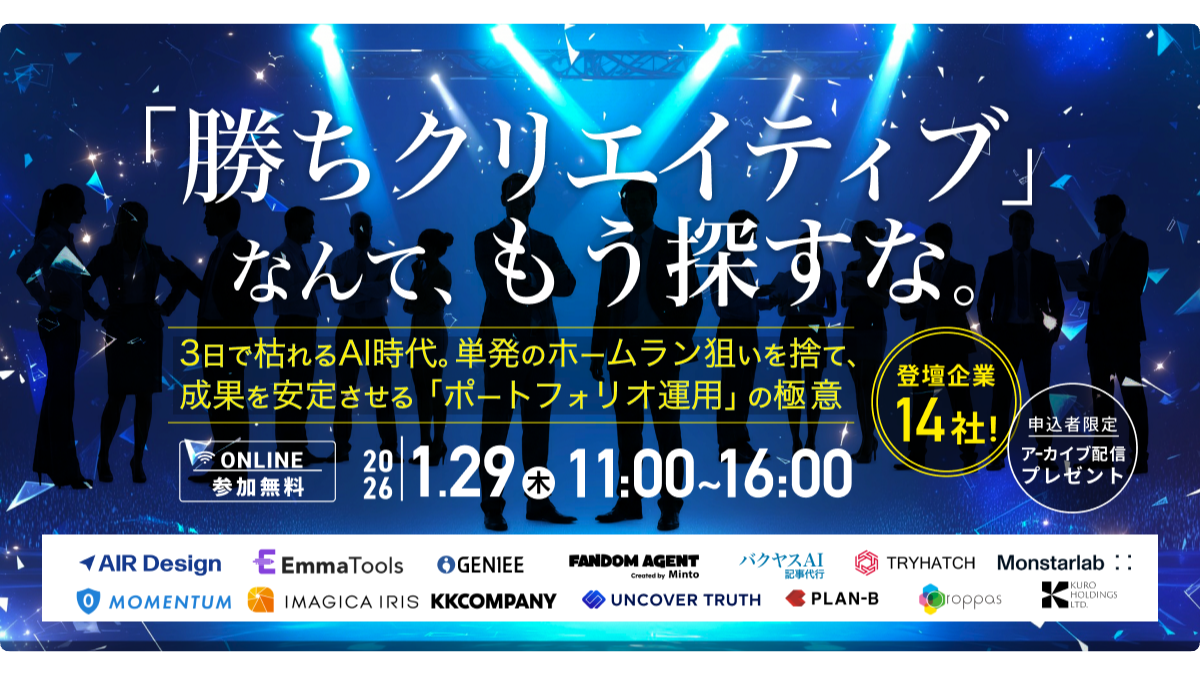Googleが導入したページエクスペリエンスアップデートは、ユーザー体験を重視した検索ランキング要因として注目を集めています。このアップデートにより、ページの読み込み速度やモバイル対応、セキュリティなどの要素がSEOに大きな影響を与えるようになりました。従来のコンテンツ品質に加えて、技術的なユーザー体験の向上が求められる時代が到来しています。本記事では、ページエクスペリエンスアップデートの基本概念から具体的な対策方法まで、SEO担当者やウェブサイト運営者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。これからのSEO対策に欠かせない知識を身につけ、検索順位の向上を目指しましょう。
- ページエクスペリエンスアップデートの基本概念と評価指標
Core Web Vitalsを中心とした複数の要素がユーザー体験として評価されます
- SEOへの具体的な影響と重要性
検索ランキング要因として技術的なユーザー体験が重視されるようになりました
- 今すぐ実践できる6つの対策方法
画像最適化やキャッシュ活用など、具体的な改善施策を実行できます
ページエクスペリエンスアップデートとは
ページエクスペリエンスアップデートは、Googleが2021年に導入した検索アルゴリズムの更新です。このアップデートでは、ウェブページがユーザーにどのような体験を提供するかを評価し、検索ランキングに反映させる仕組みが採用されています。
従来のSEOでは、コンテンツの質やキーワードの最適化、被リンクの獲得が主な評価対象でした。しかし、ページエクスペリエンスアップデートの導入により、技術的なユーザー体験も重要なランキング要因として加わりました。
アップデートの背景
Googleは「ユーザーファースト」の理念に基づき、検索結果に表示されるページが実際に快適に閲覧できるかどうかを重視するようになりました。スマートフォンの普及やインターネット利用環境の多様化に伴い、ページの表示速度や操作性がユーザー満足度に大きく影響することが明らかになっています。
特にモバイル環境では、通信速度やデバイスの性能が限られる場合があり、ページの最適化がより重要になります。このような背景から、Googleはユーザー体験を数値化して評価する仕組みを検索アルゴリズムに組み込みました。
評価される主な要素
ページエクスペリエンスアップデートでは、複数の要素が総合的に評価されます。以下の表は、主な評価要素をまとめたものです。
| 評価要素 | 概要 | 重要度 |
|---|---|---|
| Core Web Vitals | 読み込み・インタラクティブ性・視覚的安定性 | 高 |
| モバイルフレンドリー | スマートフォンでの表示最適化 | 高 |
| HTTPS対応 | セキュアな通信の確保 | 中 |
| 煩わしいインタースティシャルの排除 | ポップアップなどの適切な使用 | 中 |
これらの要素はすべてユーザー体験の質を測る指標として機能し、総合的なスコアが検索順位に影響を与えます。
導入のタイムライン
ページエクスペリエンスアップデートは、2021年6月から段階的に導入が開始されました。当初はモバイル検索を対象としていましたが、その後デスクトップ検索にも適用範囲が拡大されています。
Googleは検索ステータスダッシュボードを通じて、アップデートの進捗状況や影響範囲を公開しています。ウェブサイト運営者は、これらの情報を参考にしながら対策を進めることが効果的です。

ページエクスペリエンスアップデートは、コンテンツの質だけでなく技術面の最適化も求められる転換点となりました。まずは自サイトの現状把握から始めましょう。
Core Web Vitalsの3つの指標
ページエクスペリエンスアップデートの中核を成すのがCore Web Vitalsです。これはGoogleが定義したウェブページのユーザー体験を測定する3つの主要指標で構成されています。各指標を理解し、適切な数値を達成することがSEO対策の基盤となります。
LCP(最大コンテンツの描画)
LCP(Largest Contentful Paint)は、ページの読み込み開始からメインコンテンツが表示されるまでの時間を測定する指標です。具体的には、ビューポート内で最も大きな画像やテキストブロックが描画されるまでの時間を計測します。
Googleが推奨するLCPの目標値は2.5秒以内であり、4秒を超えると「改善が必要」と判定されます。ユーザーはページが素早く表示されることを期待しているため、LCPの最適化は離脱率の低減にも直結します。
INP(次の描画へのインタラクション)
INP(Interaction to Next Paint)は、ユーザーがページと対話してから次の画面描画が行われるまでの応答性を測定する指標です。ボタンのクリックやフォームへの入力など、ユーザーの操作に対する反応速度を評価します。
以前はFID(First Input Delay)が使用されていましたが、2024年3月からINPに置き換わりました。INPの目標値は200ミリ秒以内とされており、500ミリ秒を超えると問題があると判断されます。
CLS(累積レイアウトシフト)
CLS(Cumulative Layout Shift)は、ページの読み込み中に発生する予期しないレイアウトの移動量を測定する指標です。広告や画像の読み込みによってコンテンツが急にずれると、ユーザーが誤ってクリックしてしまうなどの問題が発生します。
CLSの目標値は0.1以下であり、0.25を超えると「改善が必要」と判定されます。視覚的な安定性を確保することで、ユーザーのストレスを軽減できます。
以下の表は、Core Web Vitalsの各指標と推奨値をまとめたものです。
| 指標 | 良好 | 改善が必要 | 不良 |
|---|---|---|---|
| LCP | 2.5秒以下 | 2.5〜4秒 | 4秒超 |
| INP | 200ms以下 | 200〜500ms | 500ms超 |
| CLS | 0.1以下 | 0.1〜0.25 | 0.25超 |
これらの指標は、Google Search ConsoleやPageSpeed Insightsなどのツールで確認できます。定期的にチェックして改善を続けることが重要です。

Core Web Vitalsの3指標は、すべてユーザーの体感品質に直結しています。まずは自サイトの現在の数値を確認してみてください。
バクヤスAI 記事代行では、
高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!
ページエクスペリエンスがSEOに与える影響
ページエクスペリエンスアップデートは、検索順位に直接影響を与えるランキング要因として機能しています。ただし、その影響度合いについては正しく理解しておく必要があります。コンテンツの質とユーザー体験のバランスを考慮したSEO戦略が求められます。
検索ランキングへの影響度
ページエクスペリエンスは、Googleが公表している数百のランキング要因の一つとして位置づけられています。重要な要素ではありますが、コンテンツの関連性や品質といった他の要因と比較すると、その影響度は相対的に限定的とされています。
Googleは「同程度の品質のコンテンツが複数ある場合、ページエクスペリエンスが良いページが優先される」と説明しています。つまり、優れたコンテンツがあることが前提であり、ユーザー体験の最適化は競合との差別化要因として機能します。
コンテンツとの関係性
SEOにおいて最も重要なのは、依然としてコンテンツの質です。ページエクスペリエンスが優れていても、ユーザーの検索意図に応えるコンテンツがなければ上位表示は困難です。
効果的なSEO戦略では、高品質なコンテンツの作成とページエクスペリエンスの最適化を並行して進めることが推奨されます。どちらか一方に偏ることなく、総合的なサイト品質の向上を目指すことが重要です。
ユーザー行動への影響
ページエクスペリエンスの改善は、直接的なランキング効果だけでなく、間接的なSEO効果ももたらします。ページの表示が速く、操作性が良いサイトでは、ユーザーの滞在時間が延び、直帰率が低下する傾向があります。
これらのユーザー行動指標の改善は、検索エンジンに対してサイトの価値を示すシグナルとなり得ます。結果として、検索順位の向上につながる可能性が考えられます。
ページエクスペリエンス改善による間接的なSEO効果
- ユーザー滞在時間の増加
- 直帰率の低下
- ページビュー数の向上
- コンバージョン率の改善

ページエクスペリエンスの改善は、SEO効果とユーザー満足度の両方を高める一石二鳥の施策です。
バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!
バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。
ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。
サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様
生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。
親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。
▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る
今すぐ実践できる6つの対策方法
ページエクスペリエンスアップデートに対応するための具体的な対策方法を紹介します。これらの施策は、専門的な技術知識がなくても取り組めるものから、開発者の協力が必要なものまで幅広く含まれています。優先度の高いものから順に実施していくことが効果的です。
画像の最適化を行う
画像ファイルのサイズは、ページの読み込み速度に大きな影響を与えます。適切なフォーマットの選択と圧縮処理を行うことで、LCPの改善が期待できます。
WebPやAVIFなどの次世代画像フォーマットを使用することで、画質を維持しながらファイルサイズを大幅に削減できます。また、遅延読み込み(lazy loading)を実装することで、ファーストビュー以外の画像の読み込みを後回しにできます。
画像最適化のチェックポイント
- WebPまたはAVIF形式への変換
- 適切な圧縮率の設定
- レスポンシブ画像の実装
- lazy loadingの設定
キャッシュを活用する
ブラウザキャッシュを適切に設定することで、リピーターのページ読み込み速度を大幅に改善できます。静的ファイル(CSS、JavaScript、画像など)に対して適切なキャッシュヘッダーを設定しましょう。
CDN(Content Delivery Network)を利用することで、地理的に分散したサーバーからコンテンツを配信し、世界中のユーザーに対して高速な表示を実現できます。
JavaScriptの読み込みを最適化する
JavaScriptファイルの読み込みは、ページのレンダリングをブロックする可能性があります。不要なJavaScriptを削除し、必要なものは非同期読み込みに変更することで、INPの改善につながります。
具体的には、asyncやdefer属性を使用してスクリプトの読み込みタイミングを制御します。また、使用していないJavaScriptライブラリがあれば削除を検討しましょう。
CSSを効率化する
CSSファイルのサイズが大きいと、ページの初期表示に時間がかかります。クリティカルCSSを抽出してインライン化し、残りのCSSは非同期で読み込む手法が効果的です。
また、未使用のCSSセレクターを削除することで、ファイルサイズを削減できます。自動化ツールを活用して、定期的にCSSの最適化を行うことが推奨されます。
レイアウトシフトを防止する
CLSの改善には、画像や広告のサイズを事前に指定することが重要です。width属性とheight属性を画像タグに設定することで、ブラウザが読み込み前にスペースを確保できます。
動的に挿入されるコンテンツ(広告や埋め込み要素)には、あらかじめ適切な高さを設定したコンテナを用意しておくことが効果的です。
以下の表は、レイアウトシフトの主な原因と対策をまとめたものです。
| 原因 | 対策 |
|---|---|
| サイズ未指定の画像 | width/height属性の追加 |
| 動的に挿入される広告 | 固定サイズのコンテナを用意 |
| Webフォントの読み込み | font-displayプロパティの設定 |
| 遅延読み込みコンテンツ | プレースホルダーの設置 |
サーバー応答時間を短縮する
サーバーの応答時間(TTFB: Time to First Byte)が長いと、すべての指標に悪影響を与えます。サーバーの性能向上やデータベースクエリの最適化を検討しましょう。
共有ホスティングを使用している場合は、VPSや専用サーバーへの移行を検討することも一つの選択肢です。また、サーバーサイドキャッシュの導入も効果的な対策となります。

6つの対策は優先度をつけて取り組むのがコツです。まずは画像最適化から始めてみてはいかがでしょう。
測定ツールの活用方法
ページエクスペリエンスの改善には、現状を正確に把握することが不可欠です。Googleが提供する公式ツールを活用して、定期的にサイトのパフォーマンスを測定・監視しましょう。各ツールの特徴を理解し、目的に応じて使い分けることが効果的です。
PageSpeed Insightsの使い方
PageSpeed Insightsは、URLを入力するだけでページのパフォーマンスを分析できる無料ツールです。Core Web Vitalsの各指標に加えて、改善のための具体的な提案も表示されます。
ラボデータ(シミュレーション環境での測定)とフィールドデータ(実際のユーザーデータ)の両方を確認できるため、より正確な状況把握が可能です。
Search Consoleでの確認方法
Google Search Consoleでは、サイト全体のCore Web Vitalsレポートを確認できます。ページごとのステータスが「良好」「改善が必要」「不良」の3段階で表示され、問題のあるページを特定できます。
ページエクスペリエンスレポートでは、モバイルとデスクトップそれぞれの状況を確認でき、HTTPS対応やモバイルフレンドリーの状態も併せてチェックできます。
Chrome DevToolsの活用
開発者向けのツールとして、Chrome DevToolsのLighthouseパネルが役立ちます。詳細なパフォーマンス診断と、コード単位での改善提案を受けることができます。
Performanceパネルでは、ページの読み込みプロセスを視覚的に確認でき、ボトルネックとなっている箇所を特定するのに効果的です。
以下の表は、各ツールの特徴と用途をまとめたものです。
| ツール名 | 主な用途 | データの種類 |
|---|---|---|
| PageSpeed Insights | 個別ページの診断 | ラボ+フィールド |
| Search Console | サイト全体の監視 | フィールド |
| Chrome DevTools | 詳細な技術分析 | ラボ |
効果的な測定のためのチェックポイント
- 定期的な測定スケジュールの設定
- 改善前後の数値記録
- 複数のツールでのクロスチェック
- モバイルとデスクトップ両方の確認

測定ツールは無料で使えるものがほとんどです。まずはPageSpeed Insightsで現状を確認することから始めてみましょう!
よくある質問
- ページエクスペリエンスアップデートはいつから適用されていますか
-
ページエクスペリエンスアップデートは2021年6月から段階的に導入が開始されました。モバイル検索への適用から始まり、その後デスクトップ検索にも適用範囲が拡大されています。現在はすべての検索結果に対して適用されている状態です。
- Core Web Vitalsの数値が悪いと必ず検索順位が下がりますか
-
Core Web Vitalsはランキング要因の一つですが、コンテンツの関連性や品質ほど決定的な影響力はありません。数値が悪くても、コンテンツの質が高ければ上位表示される可能性はあります。ただし、同程度の品質のコンテンツが複数ある場合、ページエクスペリエンスが良いページが優先される傾向があります。
- ページエクスペリエンスの改善にはどのくらいの期間がかかりますか
-
改善にかかる期間はサイトの規模や現状の問題点によって異なります。技術的な変更を実施してから、Google Search Consoleのレポートに反映されるまでには数週間程度かかることがあります。検索順位への影響についても、即座に表れるものではなく、時間をかけて徐々に変化する傾向があります。
まとめ
ページエクスペリエンスアップデートは、Googleがユーザー体験を重視する姿勢を示した重要なアルゴリズム更新です。Core Web Vitalsを中心とした技術的な指標が検索ランキングに影響を与えるようになりました。
対策としては、画像の最適化、キャッシュの活用、JavaScriptやCSSの効率化、レイアウトシフトの防止、サーバー応答時間の短縮などが効果的です。これらの施策を優先度をつけて実施することで、ユーザー体験とSEOの両方を改善できます。
ページエクスペリエンスの改善は一度行えば終わりではなく、継続的な取り組みが必要です。定期的に測定ツールを活用して現状を把握し、改善を続けることで、長期的な検索順位の向上が期待できます。まずは自サイトの現状を確認するところから始めてみましょう。