「サブドメインを使うとSEOに悪影響があるのでは」と心配される方は少なくありません。しかし、サブドメインとサブディレクトリの選択は、単純にどちらが良いという問題ではなく、サイトの目的や運用方針によって最適解が変わってきます。Googleは両者を適切に評価できると公式に発表していますが、実際の運用においては、ドメインパワーの分散や管理コストなど、考慮すべきポイントが多く存在します。本記事では、サブドメインの基本的な仕組みからSEOへの影響、そしてサブディレクトリとの使い分け方まで、具体的な判断基準とともに徹底解説します。
- サブドメインの基本的な仕組みと特徴
サブドメインはメインドメインの前に文字列を付加した独立性の高いURLで、別サイトとして扱われる特性があります
- サブドメインがSEOに与える具体的な影響
Googleは適切に評価できると発表していますが、ドメインパワーの分散や被リンク効果の違いに注意が必要です
- サブドメインとサブディレクトリの正しい使い分け方
コンテンツの独立性や運用体制に応じて選択することで、SEO効果を最大化できます
サブドメインとは何か
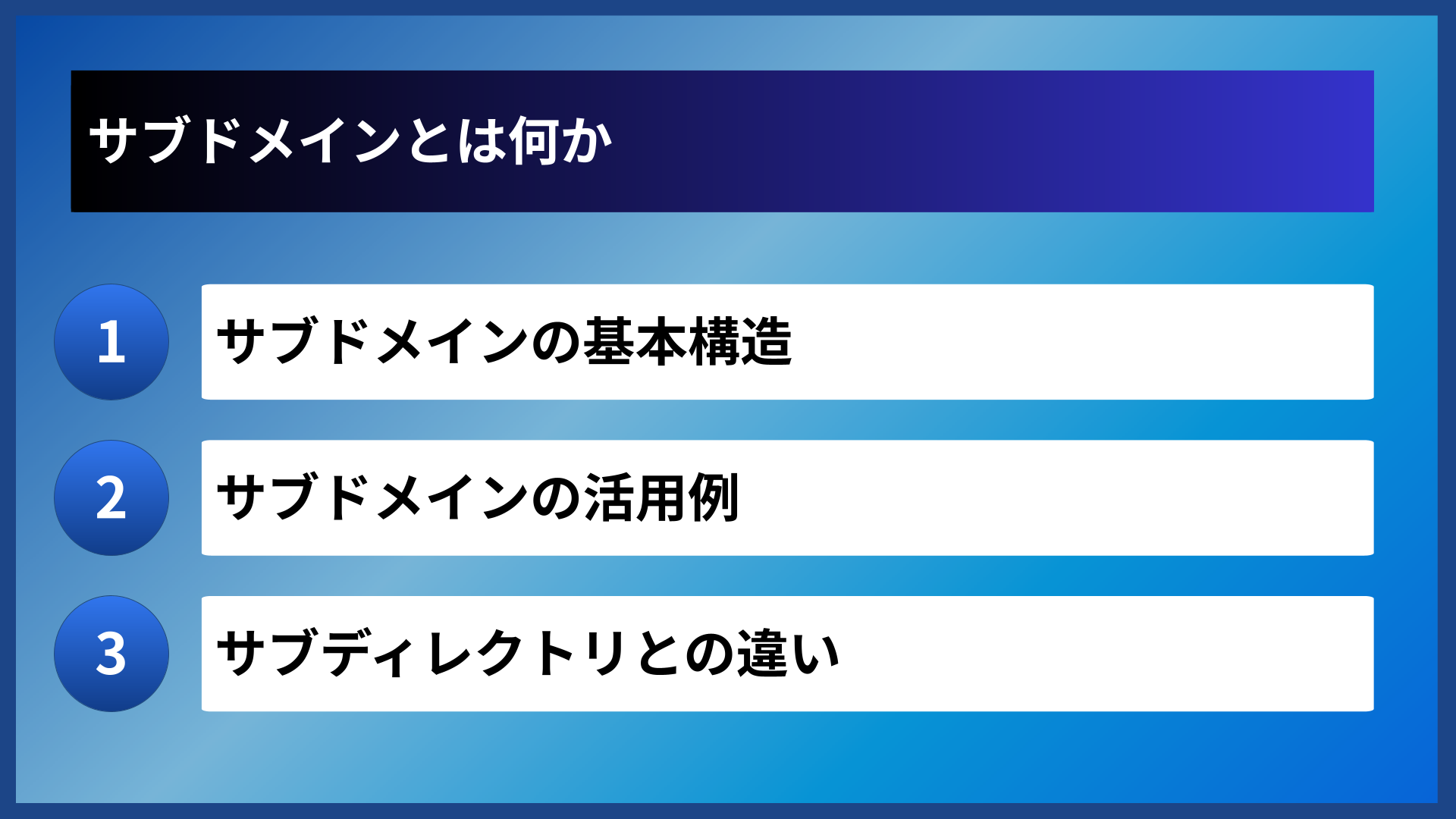
サブドメインの基本構造
サブドメインは「サブドメイン名.ドメイン名.トップレベルドメイン」という3層構造で成り立っています。具体的には「blog.example.com」の場合、「blog」がサブドメイン、「example」がセカンドレベルドメイン、「.com」がトップレベルドメインとなります。
サブドメインの設定は、利用しているサーバーやドメイン管理画面から比較的簡単に行えます。多くのレンタルサーバーでは、無制限または一定数までのサブドメイン作成が許可されていることが一般的です。
サブドメインの活用例
実際のビジネスシーンでは、様々な形でサブドメインが活用されています。代表的な例として、ブログ、ECサイト、会員専用ページ、多言語サイトなどがサブドメインで運用されることが多いです。
以下の表は、サブドメインの代表的な活用パターンをまとめたものです。
| サブドメイン例 | 用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| blog.example.com | ブログ・メディア | 情報発信を独立して運用 |
| shop.example.com | ECサイト | 決済機能を分離して管理 |
| support.example.com | サポートサイト | ヘルプコンテンツを集約 |
| en.example.com | 多言語対応 | 言語別にサイトを分離 |
このように、メインサイトとは異なる目的や機能を持つコンテンツを分離する際に、サブドメインは有効な選択肢となります。
サブディレクトリとの違い
サブドメインとよく比較されるのがサブディレクトリです。サブディレクトリは「example.com/blog/」のようにドメインの後ろにフォルダ構造として追加される形式で、メインドメインの一部として扱われます。
一方、サブドメインは技術的には別のサイトとして認識される傾向があります。この違いがSEOにおいて重要な意味を持つため、次のセクションで詳しく解説します。

サブドメインの基本を押さえておくと、SEOへの影響も理解しやすくなりますよ。まずは自社サイトの構造を確認してみましょう。

サブドメインのSEOへの影響
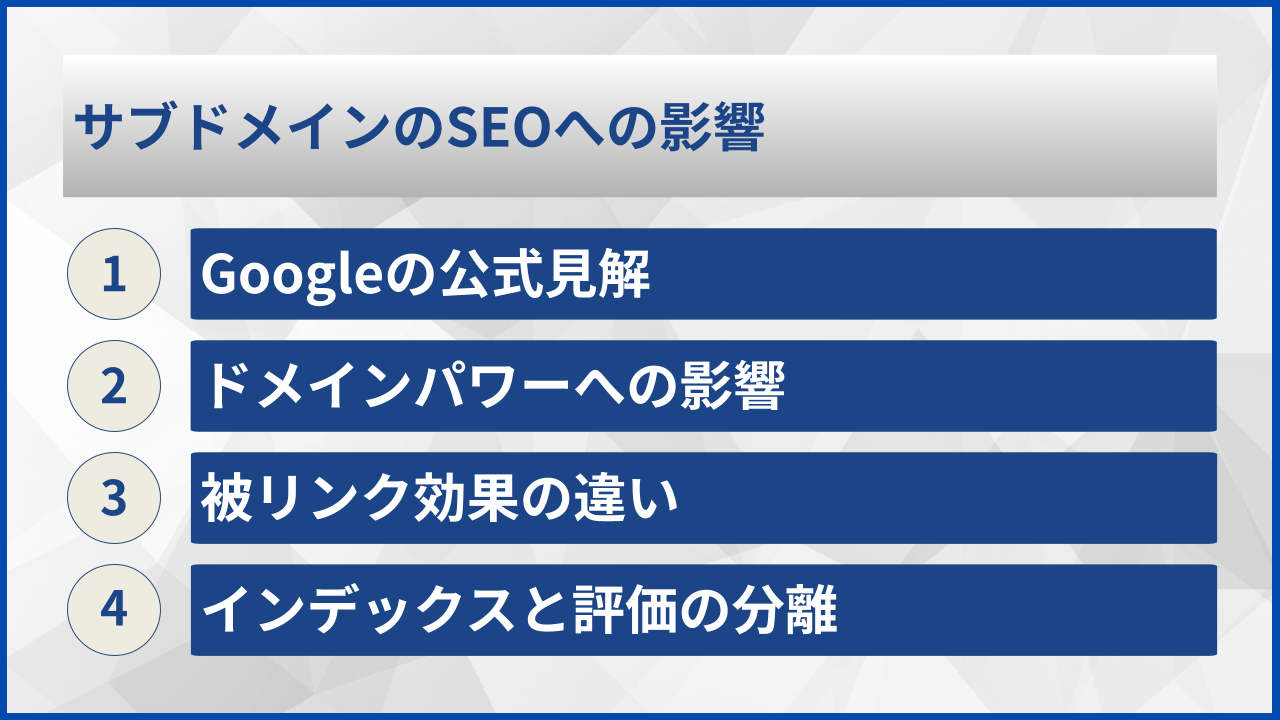
Googleの公式見解
Googleのジョン・ミューラー氏は、サブドメインとサブディレクトリのどちらを使用してもGoogleは適切にクロールし評価できると明言しています。つまり、技術的な観点からは、どちらを選んでも検索順位に直接的な優劣は生じないとされています。
ただし、これはGoogleの認識能力についての説明であり、サイト運用者が考慮すべき間接的な影響については別の問題となります。サブドメインを選択した場合の運用上の特性を理解することが重要です。
ドメインパワーへの影響
サブドメインを使用する際に最も注意すべき点の一つが、ドメインパワーの分散です。サブドメインは検索エンジンから別サイトとして認識されやすいため、メインドメインが持つ評価が直接引き継がれにくい傾向があります。
新しくサブドメインでサイトを立ち上げた場合、ある程度ゼロからの評価構築が必要になることがあります。これは、長年運用してきたメインドメインの信頼性を活かしたい場合には不利に働く可能性があります。
被リンク効果の違い
被リンクの効果についても、サブドメインとサブディレクトリでは違いが生じる場合があります。サブディレクトリであれば、獲得した被リンクの効果がドメイン全体に波及しやすいと考えられています。
一方、サブドメインへの被リンクは、そのサブドメイン内での評価向上には寄与しますが、メインドメインへの直接的な効果は限定的になる可能性があります。リンクビルディング戦略を立てる際には、この点を考慮に入れる必要があります。
インデックスと評価の分離
Googleはサブドメインを別サイトとして扱う傾向があるため、検索結果においても別々のサイトとして表示されることがあります。これは一つの検索結果に複数の自社ページを表示させたい場合にはメリットとなることもあります。
しかし、サイト全体としてのコンテンツ量や更新頻度が分散されてしまうというデメリットも存在します。SEOの観点では、コンテンツを集約してドメイン全体の価値を高める戦略が有効な場合も多いです。
以下の表で、サブドメインのSEO面でのメリットとデメリットを整理します。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| ドメイン評価 | 独立した評価を構築可能 | メインの評価を引き継ぎにくい |
| 被リンク効果 | サブドメイン内で集中 | メインへの波及が限定的 |
| 検索結果表示 | 複数サイト表示の可能性 | コンテンツ量の分散 |
| ペナルティリスク | 影響を分離できる | リスク分散が必要 |
このように、サブドメインのSEO影響は一概に良し悪しを判断できるものではありません。自社の状況に応じた判断が求められます。

SEOへの影響は状況次第で変わります。重要なのは、自社サイトの目的に合った選択をすることですね。
バクヤスAI 記事代行では、
高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

サブドメインを選ぶべきケース
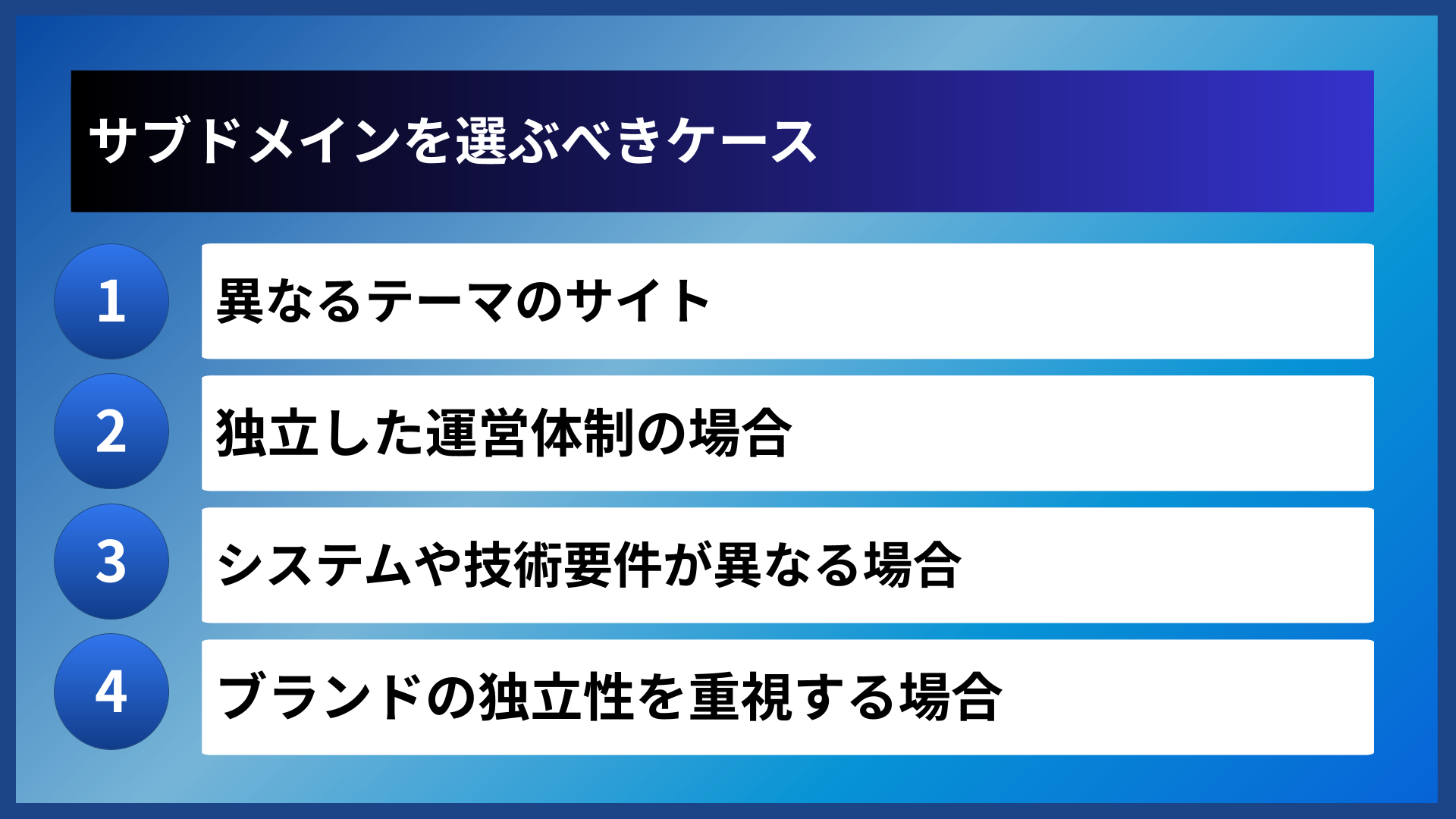
異なるテーマのサイト
メインサイトとは明確に異なるテーマや分野のコンテンツを展開する場合、サブドメインは効果的な選択肢となります。たとえば、企業のコーポレートサイトとは別に、技術ブログやユーザーコミュニティを運営する場合などが該当します。
テーマが異なるコンテンツを無理に同一ドメイン内に混在させると、サイト全体の専門性が薄まる可能性があります。サブドメインで分離することで、各サイトのテーマ性を明確に保てます。
独立した運営体制の場合
事業部や担当チームが異なり、それぞれが独立してサイトを運営する場合も、サブドメインが適しています。更新権限やコンテンツ管理を完全に分離できるため、運用上のトラブルを防ぎやすくなります。
複数のチームが一つのサイトを共同管理すると、更新タイミングの調整やコンテンツの整合性維持に労力がかかることがあります。サブドメインによる分離は、こうした運用課題を解決する手段となります。
システムや技術要件が異なる場合
ECサイトと情報サイトなど、必要なシステムや技術スタックが大きく異なる場合にも、サブドメインは有効です。異なるCMSやフレームワークを使用する場合、サブドメインで分離することで技術的な制約を回避できます。
たとえば、メインサイトはWordPressで運用しながら、ECサイト部分はShopifyなど専用のプラットフォームを使用するケースが考えられます。このような場合、サブドメインでの運用が現実的な選択となります。
ブランドの独立性を重視する場合
複数のサービスやブランドを展開している企業では、各ブランドの独立性を保つためにサブドメインを活用することがあります。ユーザーに対して、それぞれが独立したサービスであることを明確に伝えられます。
ただし、この場合は各サブドメインそれぞれでSEO施策を行う必要があるため、リソースの配分を慎重に検討する必要があります。ブランド戦略とSEO戦略のバランスを考慮した判断が求められます。

サブドメインは「分離する明確な理由がある場合」に選ぶのがポイントです。目的なく分けるのは避けましょう。
バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!
バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。
ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。
サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様
生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。
親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。
▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る
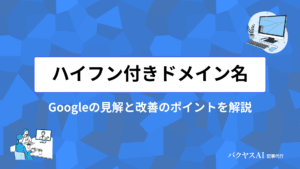
サブディレクトリを選ぶべきケース
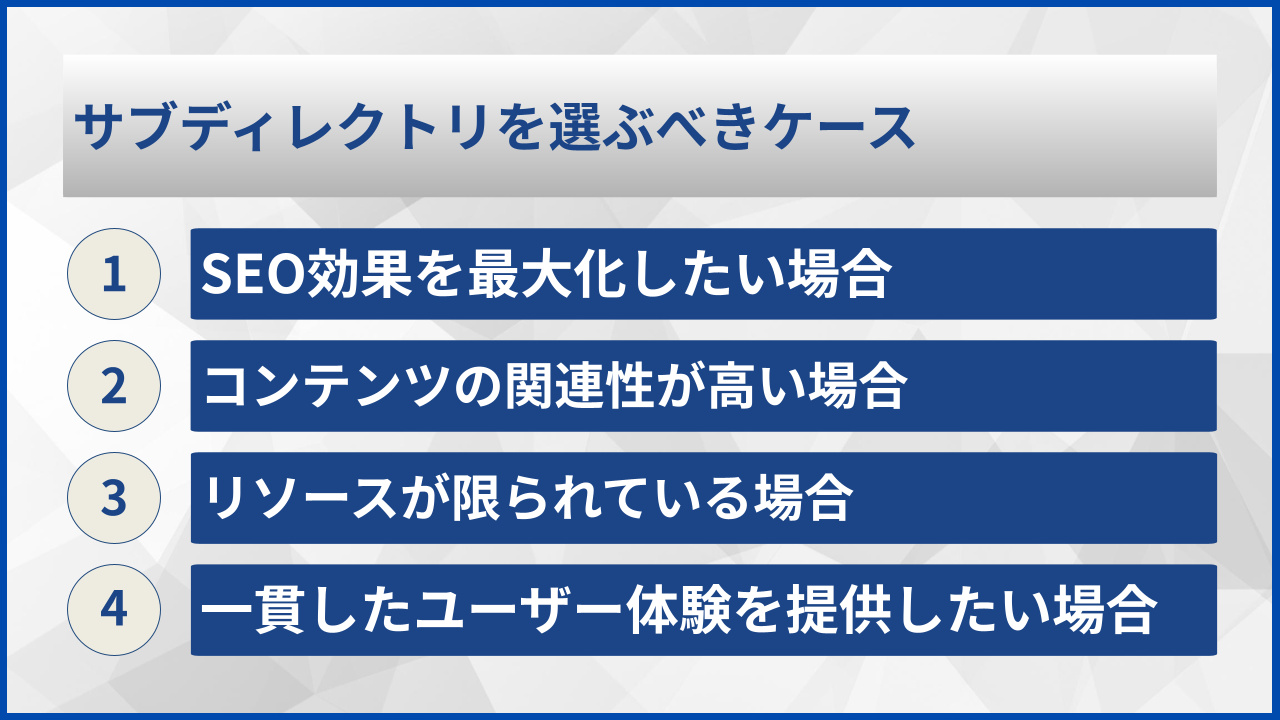
SEO効果を最大化したい場合
メインドメインがすでに一定の評価を得ている場合、その評価を新しいコンテンツにも活かしたいならサブディレクトリが適しています。サブディレクトリで追加したコンテンツは、既存のドメインパワーの恩恵を受けやすい傾向があります。
新規コンテンツの初期段階でも、メインドメインの信頼性により、インデックスやランキングにおいて有利なスタートを切れる可能性があります。
コンテンツの関連性が高い場合
追加するコンテンツがメインサイトのテーマと関連している場合は、サブディレクトリでの運用が効果的です。関連性の高いコンテンツを同一ドメイン内に集約することで、サイト全体の専門性と網羅性を高められます。
たとえば、製品紹介サイトに関連するブログや活用事例を追加する場合、サブディレクトリとして「example.com/blog/」や「example.com/case-study/」のように構成することで、トピックの一貫性を保てます。
リソースが限られている場合
サブドメインを別サイトとして運用する場合、それぞれにSEO施策や被リンク獲得の取り組みが必要になります。リソースが限られている場合は、一つのドメインに集中してSEO対策を行う方が効率的です。
サブディレクトリであれば、コンテンツ追加によるドメイン全体の価値向上が期待でき、限られたリソースを効果的に活用できます。
以下の表で、サブディレクトリとサブドメインの選択基準を整理します。
| 判断基準 | サブディレクトリ向き | サブドメイン向き |
|---|---|---|
| テーマの関連性 | メインと関連が高い | メインと異なるテーマ |
| 運営体制 | 同一チームで管理 | 独立したチームで管理 |
| 技術要件 | 同一システムで運用 | 異なるシステムが必要 |
| SEO戦略 | ドメイン評価を集中 | 独立した評価構築 |
この表を参考に、自社の状況に合った選択を検討してみてください。
一貫したユーザー体験を提供したい場合
ユーザーがサイト内を回遊する際、サブディレクトリであればURL構造の一貫性が保たれます。ブログから製品ページへ、活用事例から問い合わせページへといった導線も自然に構築できます。
サブドメインの場合、ユーザーが別サイトに移動したと認識してしまう可能性があり、サイト全体の回遊率に影響することがあります。ユーザー体験を重視する場合は、サブディレクトリが適しています。

迷ったらサブディレクトリを選ぶのが無難です。ドメインパワーを集中させられるメリットは大きいでしょう。
サブドメインSEOの実践ポイント
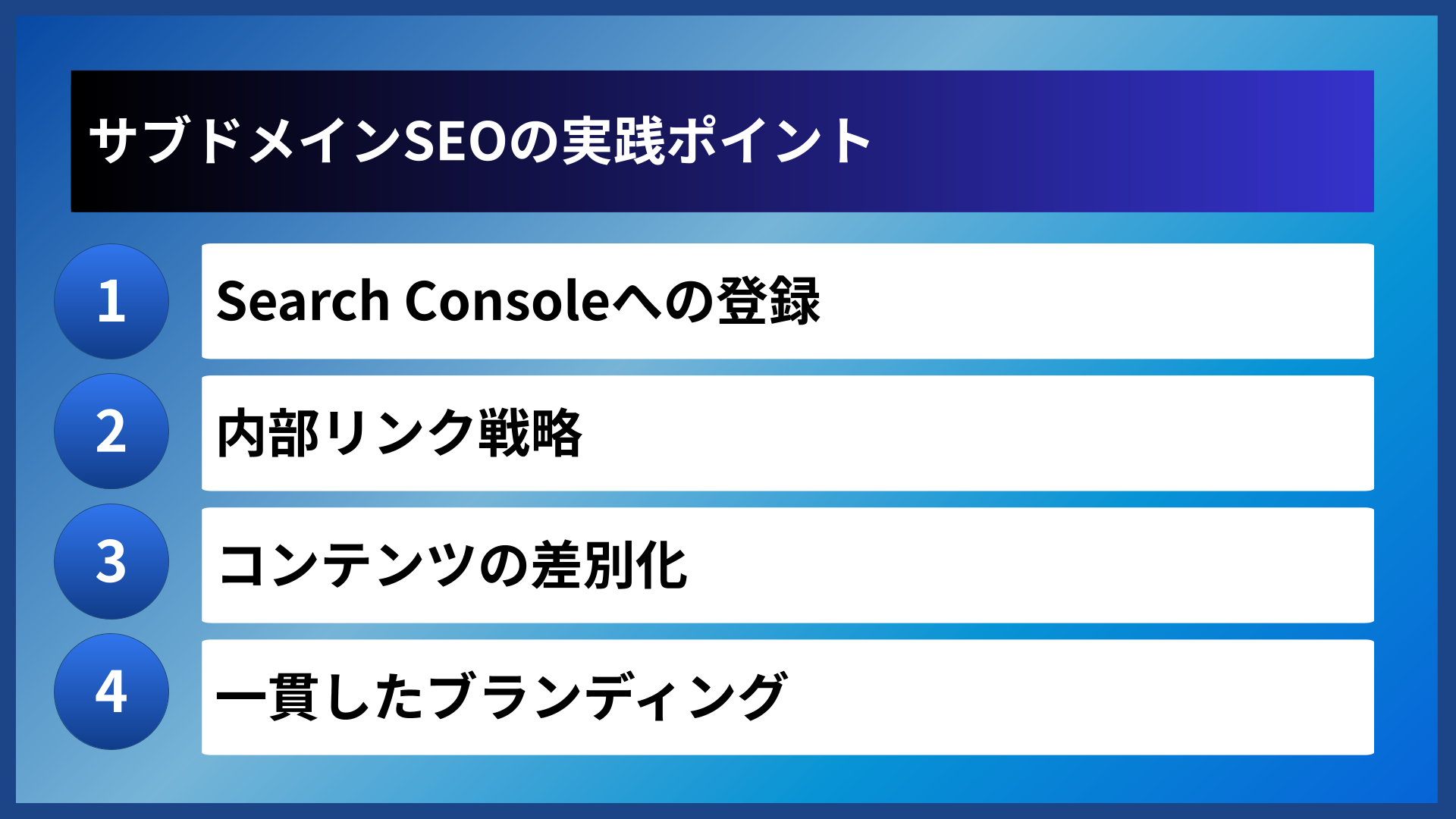
Search Consoleへの登録
サブドメインはGoogle Search Consoleにおいて別プロパティとして扱われます。新しくサブドメインを作成したら、必ずSearch Consoleに個別に登録し、インデックス状況やエラーを監視できる状態にしておきましょう。
また、サブドメイン専用のサイトマップを作成し、Search Consoleから送信することで、効率的なクロールとインデックスを促進できます。
内部リンク戦略
サブドメインとメインドメイン間のリンクは、技術的には外部リンクとして扱われる傾向があります。しかし、適切な相互リンクを設置することで、ユーザーの回遊性向上と評価の連携が期待できます。
グローバルナビゲーションやフッターに相互リンクを設置し、ユーザーが両サイト間をスムーズに移動できるよう設計することが重要です。
コンテンツの差別化
サブドメインとメインドメインで類似したコンテンツを公開してしまうと、検索エンジンから重複コンテンツと判断される可能性があります。それぞれのサイトで扱うテーマや内容を明確に差別化しておく必要があります。
コンテンツの役割分担を事前に決め、どちらのサイトでどのような情報を発信するか明確な方針を持っておきましょう。これにより、カニバリゼーションを防ぎ、それぞれのサイトが適切に評価されやすくなります。
一貫したブランディング
サブドメインで別サイトを運用する場合でも、デザインやトーンに一貫性を持たせることで、ユーザーに同一ブランドであることを認識してもらえます。これはユーザー体験の向上だけでなく、ブランド認知の面でも効果的です。
ロゴやカラースキーム、フォントなどのビジュアル要素を統一し、ユーザーがサイト間を移動しても違和感を感じないよう配慮しましょう。

サブドメインを選んだ場合も、正しく対策すればSEO効果は十分に得られます。基本を押さえて運用していきましょう!
よくある質問
- サブドメインとサブディレクトリ、SEO的にはどちらが有利ですか
-
Googleは公式に両者を同等に評価できると発表しています。ただし、実務上はドメインパワーを集中させやすいサブディレクトリの方が、限られたリソースでSEO効果を得やすい傾向があります。メインドメインと関連性の高いコンテンツであれば、サブディレクトリを選ぶことが多いです。
- すでにサブドメインで運用していますが、サブディレクトリに変更すべきですか
-
現在のサブドメインがすでに検索順位やトラフィックを獲得している場合、移行にはリスクが伴います。適切なリダイレクト設定を行っても、一時的に順位が変動する可能性があります。移行のメリットとリスクを慎重に比較検討し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
- サブドメインを複数作成するとペナルティを受けますか
-
正当な理由でサブドメインを複数運用することは問題ありません。ただし、同じ内容のコンテンツを複数のサブドメインで公開するなど、検索エンジンを欺く目的での使用は避けるべきです。各サブドメインが独自の価値を持つコンテンツを提供していれば、ペナルティの心配は基本的にありません。
- サブドメインの被リンクはメインドメインのSEOに効果がありますか
-
サブドメインへの被リンクは、主にそのサブドメイン自体の評価向上に寄与します。メインドメインへの直接的な効果は限定的と考えられています。ただし、ブランド全体の認知度向上や間接的な流入増加には貢献する可能性があります。
まとめ
サブドメインは、メインドメインの前に文字列を追加して作成される独立性の高いURL形式です。Googleは公式にサブドメインとサブディレクトリを同等に評価できると発表していますが、実務上はそれぞれ異なる特性を持っています。
サブドメインは、メインサイトと異なるテーマのコンテンツを扱う場合や、独立した運営体制が必要な場合に適しています。一方、SEO効果の最大化やドメインパワーの集中を重視する場合は、サブディレクトリが有利な選択肢となることが多いです。
重要なのは、どちらが優れているかではなく、自社の目的や状況に合った選択をすることです。コンテンツの関連性、運営体制、技術要件、SEO戦略などを総合的に考慮し、最適なURL構造を選択してください。




