Webサイトのパフォーマンスを評価する指標として、Googleが提唱する「コアウェブバイタル」が注目を集めています。ページの表示速度やユーザー体験に関わるこの指標は、検索順位にも影響を与える重要な要素です。しかし、LCP・FID・CLSという専門的な用語を目にしても、具体的に何を意味するのか分からないという方も多いのではないでしょうか。本記事では、コアウェブバイタルの基本概念から3つの指標の意味、測定方法、そして実践的な改善方法まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。サイト運営者やWeb担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
- コアウェブバイタルの基本概念とSEOへの影響
コアウェブバイタルはGoogleが定めるユーザー体験の品質指標であり、検索順位に直接影響を与えます
- LCP・FID・CLSの3指標の意味と目標値
各指標には明確な基準値があり、LCPは2.5秒以内、FIDは100ミリ秒以内、CLSは0.1以下が目標です
- 実践的な測定方法と改善施策
PageSpeed InsightsやSearch Consoleを活用した測定から、画像最適化やコード改善まで具体的に取り組めます
コアウェブバイタルの基本概念
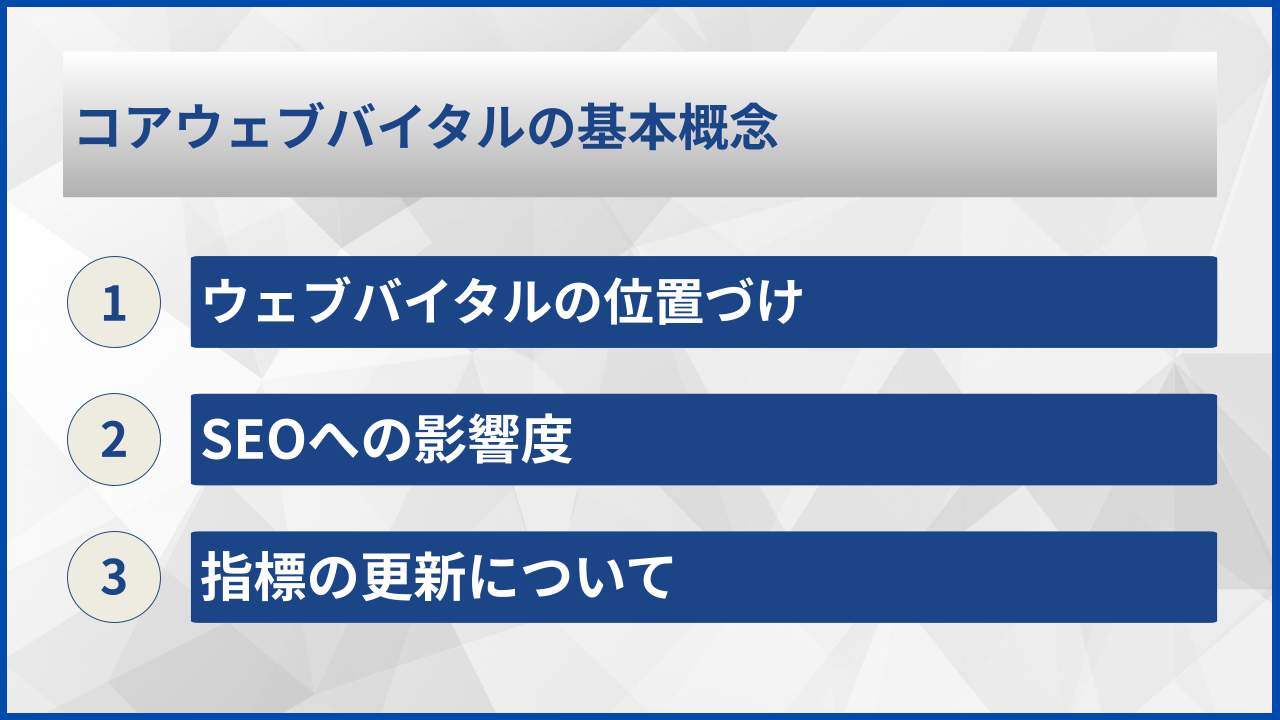
ウェブバイタルの位置づけ
ウェブバイタルは、Webサイトの品質を測定するためのGoogleの取り組み全体を指します。その中でも特に重要な3つの指標が「コア(核心)」として選定されています。
コアウェブバイタルは、読み込みパフォーマンス、インタラクティブ性、視覚的安定性という3つの側面からユーザー体験を評価します。これらは全てのWebページに共通して適用される普遍的な指標であり、サイトの種類や業界を問わず重要とされています。
SEOへの影響度
コアウェブバイタルは、Googleの検索アルゴリズムにおけるランキング要因の一つです。ただし、コンテンツの質や関連性が最も重要な要素であることに変わりはありません。
同等の品質を持つページが複数存在する場合、コアウェブバイタルのスコアが高いページが優先される傾向があります。特にモバイル検索においては、ページエクスペリエンスの重要性が高まっており、改善に取り組む価値があります。
以下の表は、コアウェブバイタルとSEOの関係性をまとめたものです。
| 要素 | SEOへの影響 | 重要度 |
|---|---|---|
| コンテンツの質 | 最も重要なランキング要因 | 最高 |
| コアウェブバイタル | ページエクスペリエンスの構成要素 | 高 |
| モバイルフレンドリー | モバイル検索での重要要因 | 高 |
指標の更新について
コアウェブバイタルの指標は、技術の進歩やユーザー行動の変化に応じて更新されることがあります。実際に2024年3月には、FID(First Input Delay)がINP(Interaction to Next Paint)に置き換えられました。
このような変更は事前に告知され、移行期間が設けられるのが通例です。サイト運営者は、Googleの公式アナウンスを定期的に確認し、最新の要件に対応することが求められます。

コアウェブバイタルはSEOの一要素ですが、ユーザー満足度を高めるという本質的な価値も忘れないでください

コアウェブバイタルの3指標を解説
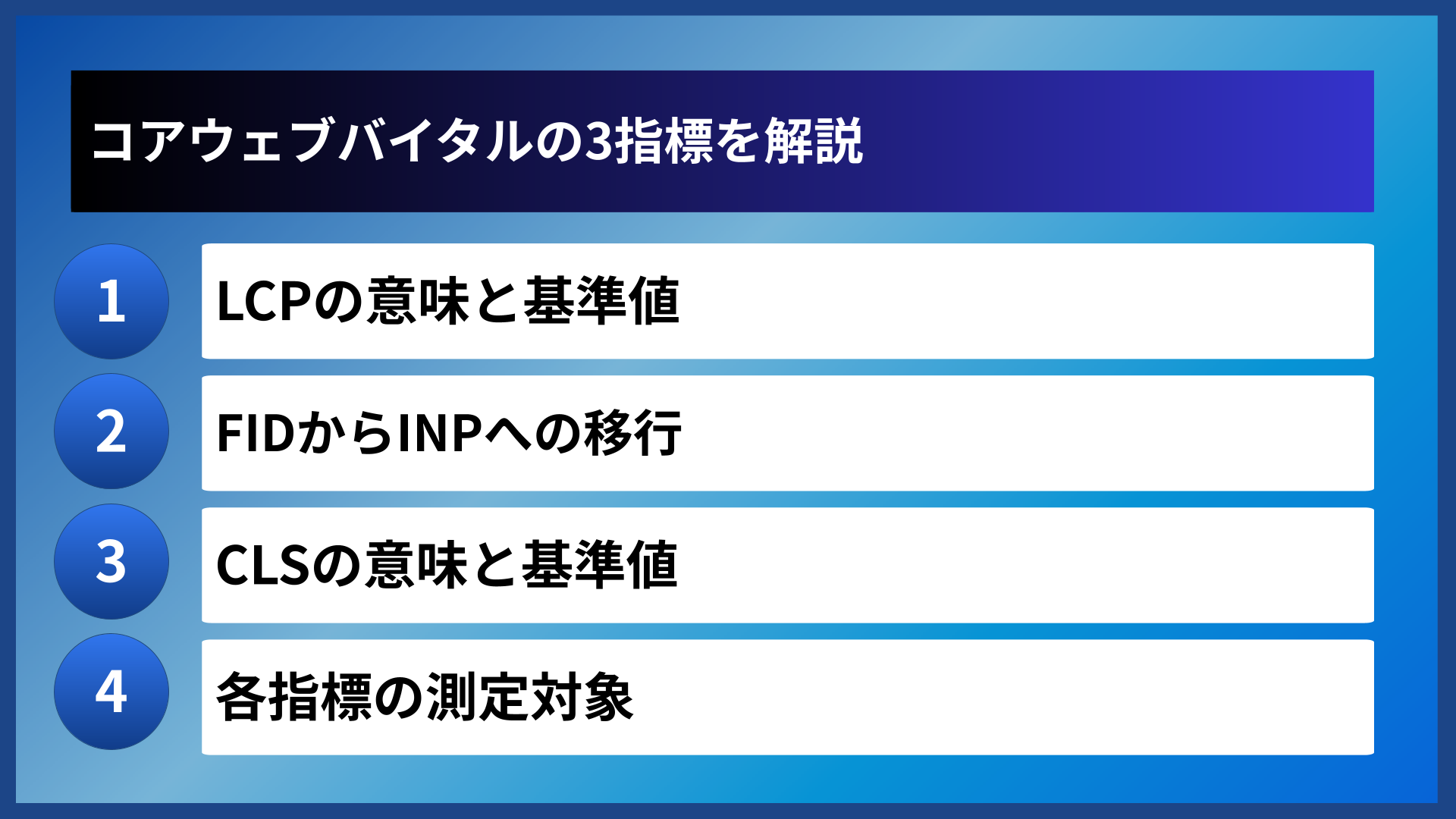
LCPの意味と基準値
LCP(Largest Contentful Paint)は、ページ内で最も大きなコンテンツ要素が表示されるまでの時間を測定します。ユーザーがページを開いてから、メインコンテンツが見えるようになるまでの体感速度を数値化した指標です。
Googleが定めるLCPの目標値は2.5秒以内であり、4秒を超えると「不良」と判定されます。最も大きなコンテンツ要素には、画像、動画のサムネイル、背景画像付きのブロック要素、テキストブロックなどが含まれます。
| 評価 | LCPの値 | ユーザー体験 |
|---|---|---|
| 良好 | 2.5秒以内 | 快適に閲覧可能 |
| 改善が必要 | 2.5秒〜4秒 | やや遅さを感じる |
| 不良 | 4秒超 | 離脱につながる |
FIDからINPへの移行
FID(First Input Delay)は、ユーザーが最初にページと対話した際の応答遅延を測定する指標でした。しかし、最初の入力のみを測定するという限界があったため、2024年3月にINP(Interaction to Next Paint)に置き換えられました。
INPは、ページ上で発生する全てのインタラクションの応答性を測定し、その中で最も遅い値を指標として採用します。目標値は200ミリ秒以内であり、500ミリ秒を超えると「不良」と判定されます。ボタンのクリックやフォームへの入力など、ユーザー操作全般の快適さを評価できるようになっています。
CLSの意味と基準値
CLS(Cumulative Layout Shift)は、ページの読み込み中に発生する予期しないレイアウトのずれを測定します。ユーザーがリンクをクリックしようとした瞬間にレイアウトが動いてしまう、といった不快な体験を数値化した指標です。
CLSの目標値は0.1以下であり、0.25を超えると「不良」と判定されます。画像や広告、動的に読み込まれるコンテンツがレイアウトシフトの主な原因となることが多いです。
3指標の目標値まとめ
- LCP:2.5秒以内(読み込み速度)
- INP:200ミリ秒以内(応答性)
- CLS:0.1以下(視覚的安定性)
各指標の測定対象
コアウェブバイタルの各指標は、フィールドデータとラボデータの両方で測定できます。フィールドデータは実際のユーザーから収集されたデータであり、より現実的な状況を反映しています。
ラボデータは開発環境でのテスト結果を示し、問題の診断や改善策の検証に役立ちます。Googleは、フィールドデータを検索順位の評価に使用しているため、実際のユーザー体験の改善が最終的な目標となります。

3つの指標はそれぞれ異なる側面を測定しています。バランスよく改善することが重要でしょう
バクヤスAI 記事代行では、
高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!

コアウェブバイタルの測定方法
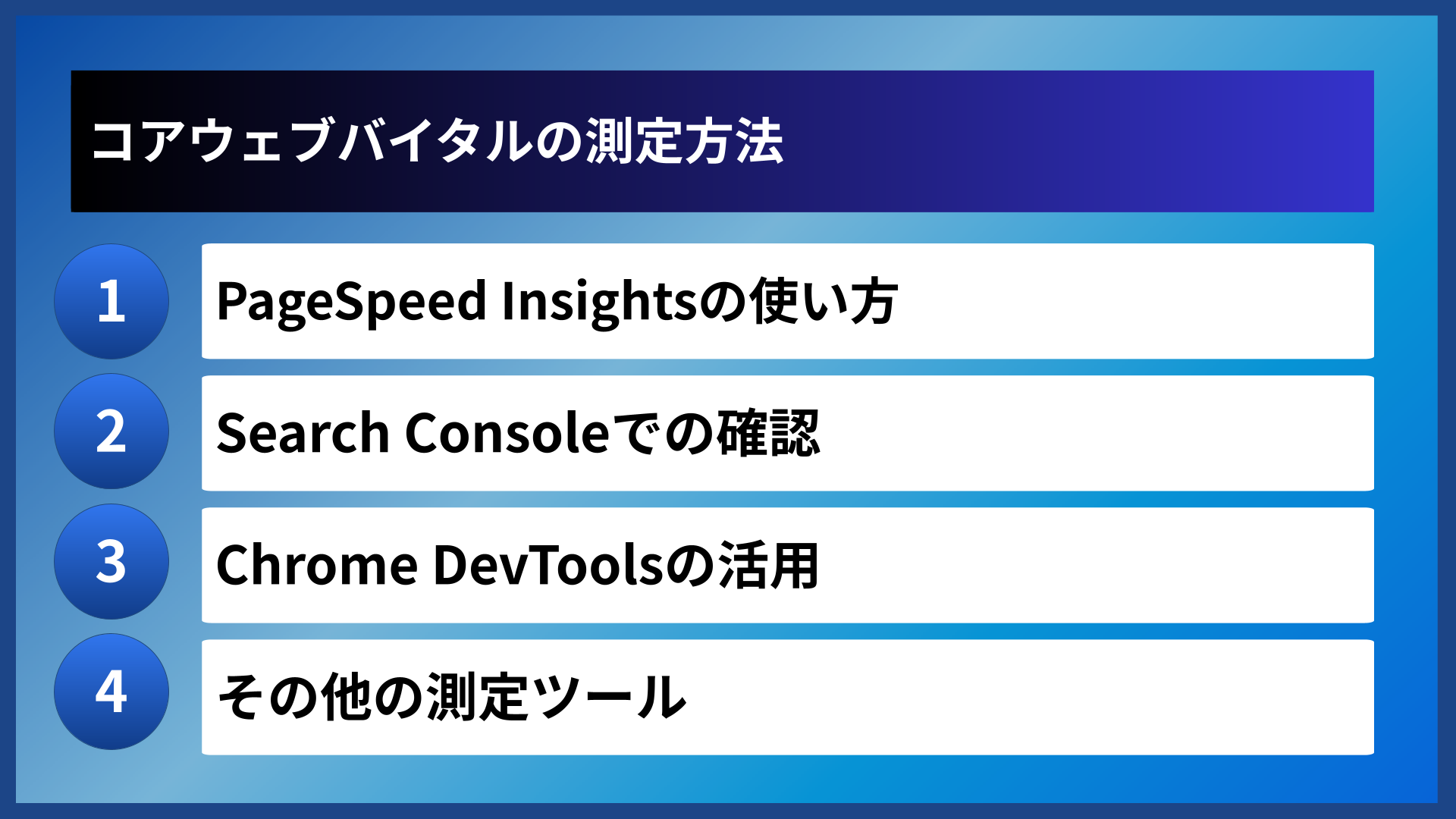
PageSpeed Insightsの使い方
PageSpeed Insightsは、Googleが提供する最も基本的な測定ツールです。URLを入力するだけで、モバイルとデスクトップ両方のパフォーマンスを分析できます。
このツールでは、フィールドデータとラボデータの両方を確認でき、具体的な改善提案も表示されます。スコアは0〜100で表示され、各指標の詳細な数値と改善のヒントを得ることができます。
PageSpeed Insightsで確認できる項目
- コアウェブバイタルの3指標の数値
- パフォーマンススコア(0〜100)
- 具体的な改善提案と優先度
- 診断結果と技術的な詳細情報
Search Consoleでの確認
Google Search Consoleでは、サイト全体のコアウェブバイタルの状況を一覧で確認できます。ページエクスペリエンスレポートから、モバイルとデスクトップそれぞれの状況を把握できます。
このツールの特徴は、実際のユーザーデータ(フィールドデータ)に基づいた評価が得られる点です。改善が必要なURLがグループ化されて表示されるため、優先度の高いページから効率的に対応できます。
Chrome DevToolsの活用
開発者向けのChrome DevToolsでは、Lighthouseパネルを使用してより詳細な分析が可能です。ローカル環境でのテストができるため、公開前の確認や改善効果の検証に適しています。
Performanceパネルでは、ページ読み込みのタイムラインを可視化でき、どの処理がボトルネックになっているかを特定できます。技術的な改善を行う際には、このツールが特に役立ちます。
その他の測定ツール
Googleが提供するツール以外にも、コアウェブバイタルを測定できるツールがあります。以下の表は、主要な測定ツールの比較をまとめたものです。
| ツール名 | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|
| PageSpeed Insights | フィールドデータとラボデータ両方 | 総合的な分析 |
| Search Console | サイト全体の状況把握 | 継続的なモニタリング |
| Chrome DevTools | 詳細な技術分析 | 開発・デバッグ |
| Web Vitals拡張機能 | リアルタイム測定 | 簡易チェック |
Chrome拡張機能の「Web Vitals」は、閲覧中のページのコアウェブバイタルをリアルタイムで表示します。日常的なチェックに便利なツールです。

まずはPageSpeed Insightsで現状を把握し、Search Consoleで継続的にモニタリングするのがおすすめです
バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!
バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。
ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。
サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様
生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。
親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。
▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

コアウェブバイタルの改善方法
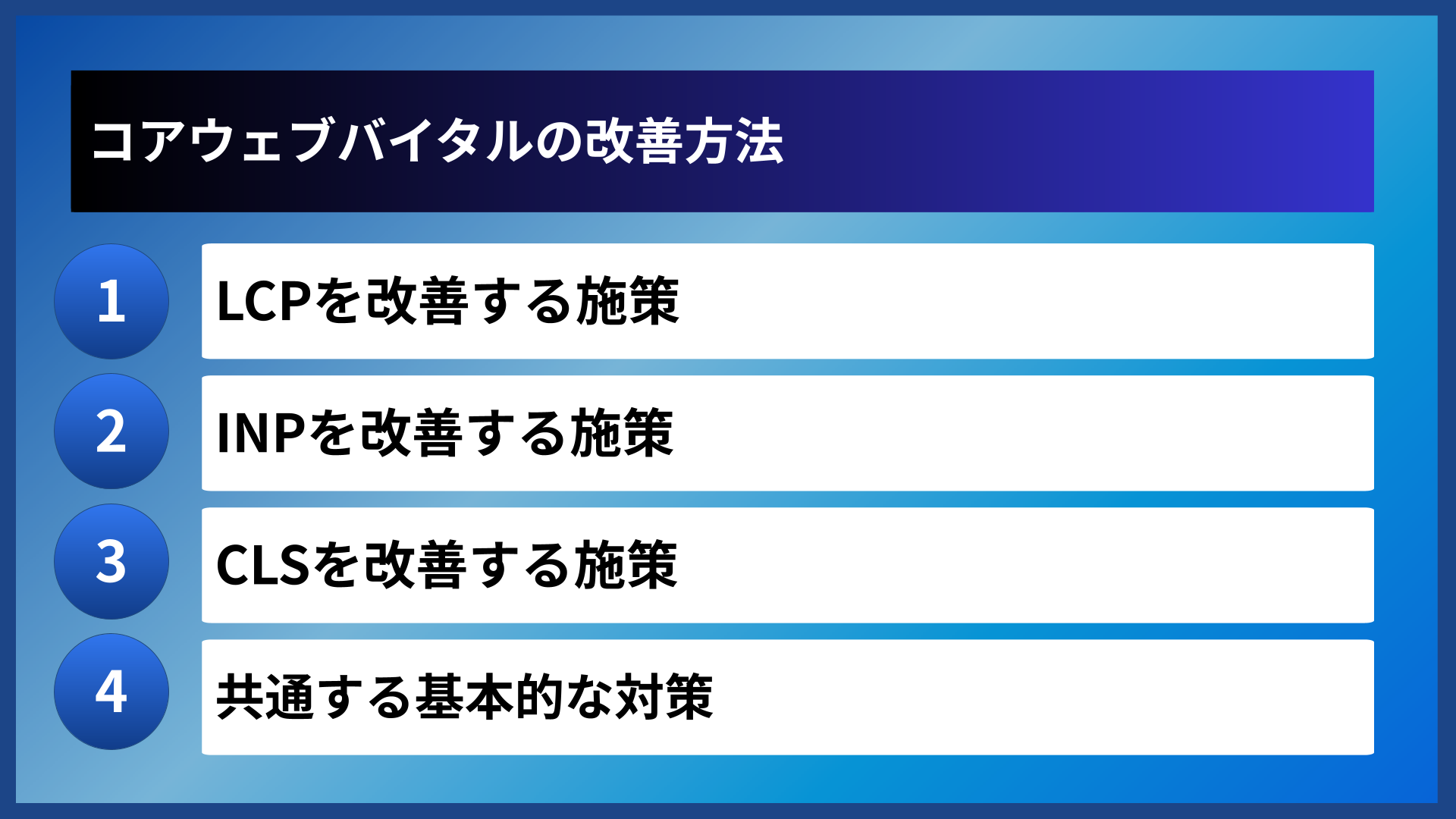
LCPを改善する施策
LCPの改善には、最大コンテンツ要素の表示速度を向上させることが必要です。多くの場合、ページ上部の大きな画像やヒーローセクションがLCPの対象となります。
画像の最適化は最も効果的なLCP改善策であり、次世代フォーマット(WebP、AVIF)の採用や適切なサイズへのリサイズが有効です。また、サーバーの応答時間を短縮することや、レンダリングをブロックするリソースを削減することも重要な施策となります。
LCP改善のチェックリスト
- 画像をWebP/AVIF形式に変換する
- 画像の遅延読み込みを適切に設定する
- CDNを活用してコンテンツ配信を高速化する
- サーバーの応答時間(TTFB)を改善する
INPを改善する施策
INP(旧FID)の改善には、JavaScriptの実行時間を短縮することが中心となります。メインスレッドをブロックする長時間のタスクを分割し、ユーザーの操作に素早く応答できる状態を維持することが目標です。
不要なJavaScriptの削除、コードの分割、サードパーティスクリプトの最適化などが効果的な施策です。また、イベントハンドラの処理を軽量化し、必要に応じて非同期処理を活用することも重要です。
CLSを改善する施策
CLSの改善には、レイアウトが予期せず動くことを防ぐための対策が必要です。特に画像や動画、広告、動的に挿入されるコンテンツが主な原因となります。
画像や動画には必ずwidth属性とheight属性を指定し、ブラウザが事前にスペースを確保できるようにすることが基本的な対策です。また、広告枠には固定サイズのプレースホルダーを設定し、Webフォントの読み込みによるテキストのちらつきを防ぐためにfont-displayプロパティを適切に設定します。
| CLSの原因 | 改善策 |
|---|---|
| サイズ未指定の画像 | width/height属性を追加 |
| 動的に読み込まれる広告 | 広告枠のサイズを事前に確保 |
| Webフォントの読み込み | font-display: swapを設定 |
| 動的コンテンツの挿入 | 挿入位置を既存コンテンツの下に |
共通する基本的な対策
すべてのコアウェブバイタル指標に効果がある基本的な対策もあります。これらは、Webサイトのパフォーマンス全般を向上させるための基盤となる施策です。
サーバーのパフォーマンス向上、CDN(コンテンツ配信ネットワーク)の活用、キャッシュの適切な設定は、どの指標にも良い影響を与えます。また、定期的なパフォーマンスモニタリングを行い、問題が発生した際に早期に対応できる体制を整えることも大切です。

改善は一度で完了するものではありません。継続的なモニタリングと改善のサイクルを回していきましょう

コアウェブバイタル改善の優先順位
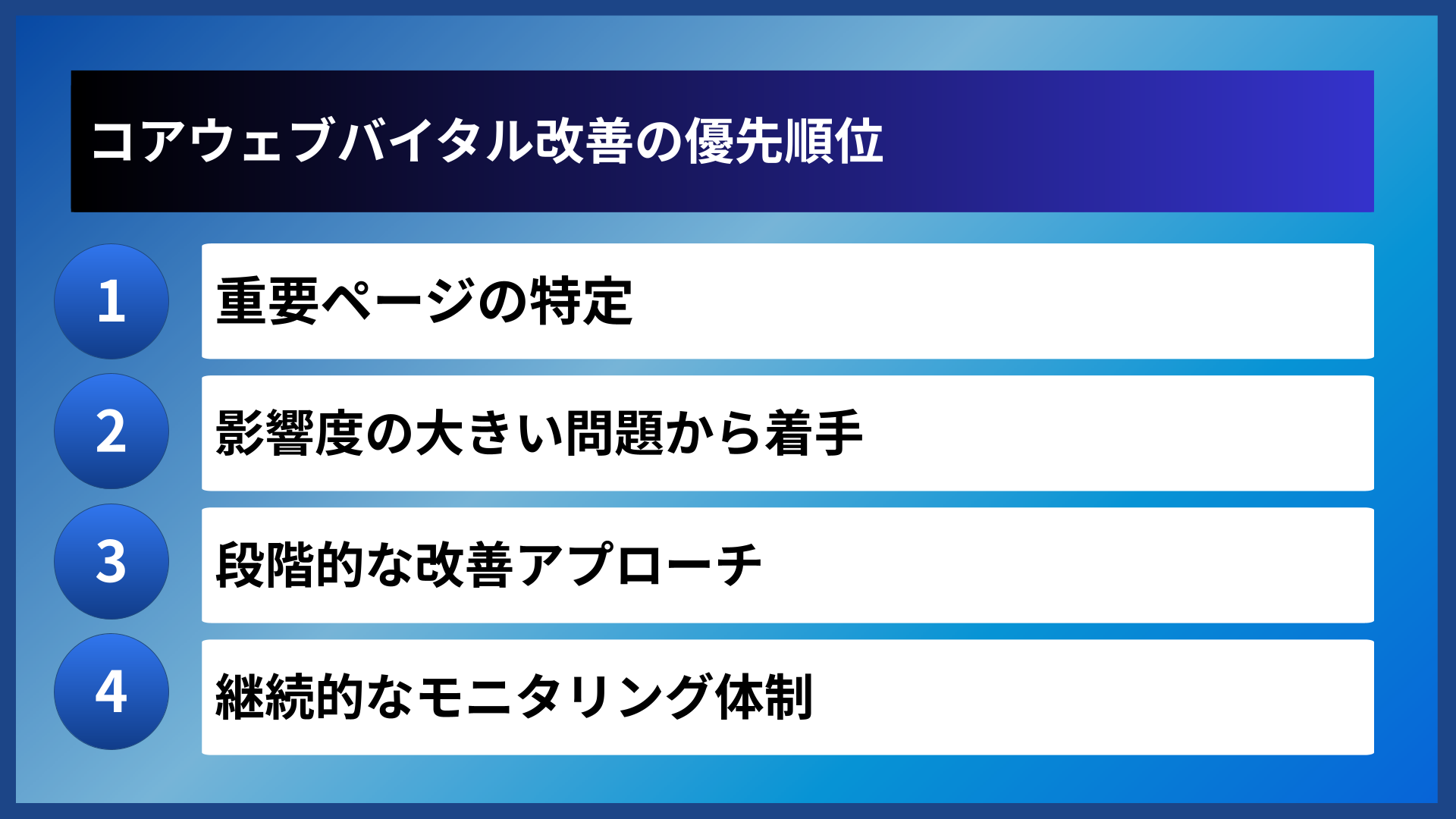
重要ページの特定
最初に改善すべきは、サイトにとって最も重要なページです。トップページ、主要なランディングページ、コンバージョンに直結するページなどが該当します。
Google Search Consoleでトラフィックの多いページを確認し、それらのページのコアウェブバイタルスコアを優先的に改善することが効果的です。改善の効果が大きいページから着手することで、サイト全体のパフォーマンス向上につながります。
影響度の大きい問題から着手
PageSpeed Insightsの診断結果では、各改善項目の影響度が表示されます。影響度の高い項目から順番に対応することで、効率的にスコアを向上させることができます。
一般的に、画像の最適化やレンダリングブロックリソースの削減は、比較的少ない工数で大きな効果を得られることが多いです。逆に、JavaScriptの大幅なリファクタリングなどは、工数がかかる割に効果が限定的な場合もあります。
優先度の高い改善項目
- 大きな画像ファイルの最適化
- 使用していないCSSやJavaScriptの削除
- サーバー応答時間の改善
- 画像のサイズ指定(CLS対策)
段階的な改善アプローチ
コアウェブバイタルの改善は、一度に全てを完璧にする必要はありません。段階的に改善を進め、各ステップで効果を確認しながら進めることが現実的です。
まずは「不良」と判定されているページを「改善が必要」レベルに引き上げ、その後「良好」を目指すという段階的なアプローチが有効です。改善のたびに測定を行い、効果を確認してから次のステップに進むことで、効率的に作業を進められます。
継続的なモニタリング体制
コアウェブバイタルは、サイトの更新やコンテンツの追加によって変動することがあります。そのため、一度改善した後も継続的なモニタリングが必要です。
Search Consoleのレポートを定期的に確認し、新たな問題が発生していないかチェックする習慣を付けましょう。また、サイトに大きな変更を加える際には、事前にパフォーマンスへの影響を検証することも重要です。

完璧を目指すよりも、まずは「不良」をなくすことから始めてみてはいかがでしょうか
よくある質問
- コアウェブバイタルが悪いと検索順位は下がりますか
-
コアウェブバイタルは検索順位を決定する要因の一つですが、コンテンツの質や関連性ほど大きな影響はありません。ただし、同等の品質を持つページ同士では、コアウェブバイタルのスコアが高いページが優先される傾向があります。そのため、可能な範囲で改善に取り組むことをおすすめします。
- FIDとINPの違いは何ですか
-
FID(First Input Delay)はユーザーが最初に行った操作への応答時間のみを測定していましたが、INP(Interaction to Next Paint)はページ上で発生する全てのインタラクションを測定対象としています。INPの方がより包括的にページの応答性を評価できるため、2024年3月にFIDからINPへの置き換えが行われました。
- コアウェブバイタルの改善にはどのくらいの時間がかかりますか
-
改善にかかる時間はサイトの状況や問題の内容によって大きく異なります。画像の最適化など簡単な施策であれば数時間から数日で効果が出ることもありますが、根本的なアーキテクチャの見直しが必要な場合は数週間から数ヶ月かかることもあります。また、Googleがフィールドデータを更新するには28日間のデータ蓄積期間が必要なため、Search Consoleに反映されるまでには時間がかかります。
- モバイルとデスクトップで別々に対策する必要がありますか
-
モバイルとデスクトップでは表示されるコンテンツや通信環境が異なるため、それぞれのスコアを確認して対策を行うことが望ましいです。特にGoogleのモバイルファーストインデックスでは、モバイル版のページが評価の基準となるため、モバイルのコアウェブバイタル改善を優先することをおすすめします。

まとめ
コアウェブバイタルは、Googleが定めるWebページのユーザー体験を測定するための重要な指標群です。LCP(読み込み速度)、INP(応答性)、CLS(視覚的安定性)の3つの指標から構成され、検索順位にも影響を与えます。
改善に取り組む際は、PageSpeed InsightsやSearch Consoleで現状を把握し、影響度の高い施策から優先的に対応することが効果的です。画像の最適化やサーバー応答時間の改善など、比較的取り組みやすい施策から始めることをおすすめします。
コアウェブバイタルの改善は一度で終わるものではなく、継続的なモニタリングと改善のサイクルを回していくことが大切です。ユーザーにとって快適なサイト体験を提供することが、結果としてSEOにも良い影響を与えるでしょう。



