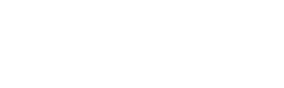画像SEO対策は、検索エンジンでの上位表示を目指すために欠かせない重要な施策です。Googleの検索結果では、通常の検索結果だけでなく、画像検索からの流入も無視できません。適切な画像SEO対策を行うことで、ウェブサイトの可視性向上と自然検索トラフィックの増加が期待できます。本記事では、画像SEO対策の基本から具体的な実践テクニックまで、初心者にも分かりやすく解説します。alt属性の設定方法、ファイル名の最適化、画像のファイルサイズ調整など、今すぐ実践できる7つの手法をマスターして、あなたのウェブサイトの検索順位向上を実現しましょう。
画像SEOの基本概念と重要性
画像SEOとは、ウェブサイトに掲載している画像を検索エンジンに正しく認識させ、検索結果での上位表示を目指す最適化手法のことです。
検索エンジンは、テキスト情報と比べて画像の内容を理解するのが困難です。そのため、適切なメタデータの設定や技術的な最適化を通じて、検索エンジンに画像の内容や価値を伝える必要があります。
検索エンジンが画像を評価する仕組み
検索エンジンは画像そのものを視覚的に認識するのではなく、周辺のテキスト情報やメタデータから画像の内容を判断しますまず、alt属性やファイル名、周辺テキストなどの情報を総合的に分析し、画像の関連性を評価しています。
近年では、AI技術の発展により画像認識技術も向上していますが、依然としてテキスト情報による補助が重要な役割を果たしています。適切な情報提供により、検索エンジンの理解度を高めることができます。
画像SEO対策がサイト全体に与える効果
画像SEO対策は、単純に画像検索からの流入だけでなく、ウェブサイト全体のSEO効果にも影響を与えます。適切に最適化された画像は、ページの読み込み速度向上やユーザビリティの改善に繋がります
また、視覚的に魅力的なコンテンツは、ユーザーの滞在時間延長や回遊率向上にも寄与し、間接的にSEO効果を高める要因となります。
画像検索における流入獲得の可能性
Google画像検索は、多くのユーザーが利用する重要な検索手段の一つです。特に、商品画像や操作方法の説明画像、インフォグラフィックなどは、画像検索からの流入が期待できる分野です。
適切な画像SEO対策により、通常の検索結果では競合が激しいキーワードでも、画像検索では上位表示を狙える可能性があります。これにより、新たな流入経路の開拓が可能になります。

画像SEO対策は単なる画像最適化ではなく、サイト全体のSEO戦略の一部として捉えることが大切ですね。

alt属性の最適化テクニック
alt属性(代替テキスト)は、画像SEO対策の中でも最も重要な要素の一つです。検索エンジンが画像の内容を理解するための主要な手がかりとなります。
適切なalt属性の設定は、検索エンジンの理解度向上だけでなく、アクセシビリティの観点からも非常に重要です。視覚障害のあるユーザーが使用するスクリーンリーダーも、alt属性の情報を読み上げて画像の内容を伝えています。
効果的なalt属性の書き方
alt属性は、画像の内容を簡潔かつ具体的に説明する必要があります文字数は50文字程度を目安とし、画像の主要な要素や目的を明確に表現します。
例えば、「画像1」や「写真」といった抽象的な表現ではなく、「スマートフォンでWebサイトを閲覧する女性」のように、具体的な状況や要素を含めて記述することが重要です。
| 良い例 | 悪い例 | 理由 |
|---|---|---|
| SEO対策のチェックリストを確認する男性 | 画像 | 具体的な内容が分かる |
| 赤いスポーツカーの正面写真 | 車の写真 | 色や種類、角度が明確 |
| エクセルでグラフを作成している画面 | パソコン画面 | 具体的な作業内容を表現 |
キーワードを含めたalt属性の設定方法
alt属性にターゲットキーワードを自然に含めることで、検索エンジンにページの関連性を伝えることができます。ただし、キーワードの詰め込みは避け、自然な文章として成立させることが重要です。
「SEO対策」をキーワードとする場合、「SEO対策の効果を分析するグラフ」のように、コンテンツの文脈に合わせてキーワードを組み込みます。無理にキーワードを繰り返したり、不自然な表現にしたりすることは避けましょう。
alt属性設定時の注意点
装飾的な画像や背景画像など、コンテンツの理解に直接関係しない画像については、空のalt属性(alt=””)を設定することが推奨されています。これにより、スクリーンリーダーが不要な情報を読み上げることを防げます
また、同じ画像を複数のページで使用する場合でも、各ページのコンテキストに応じてalt属性を調整することが大切です。画像の役割や目的が異なる場合は、それに合わせた記述を行います。
alt属性設定のチェックポイント
- 画像の内容を具体的に説明できているか
- 文字数は50文字程度に収まっているか
- ターゲットキーワードが自然に含まれているか
- 装飾画像には空のalt属性を設定しているか
- ページの文脈に合った内容になっているか

alt属性は画像の内容を的確に伝える「翻訳者」のような役割を果たしているんですね。
バクヤスAI 記事代行では、無料でLLMO診断を実施中です。

画像ファイル名の最適化方法
画像ファイル名は、検索エンジンが画像の内容を理解するための重要な手がかりの一つです。適切なファイル名の設定により、画像の検索順位向上が期待できます。
多くのウェブサイトでは、カメラで撮影した際のデフォルトファイル名「IMG_001.jpg」や「DSC_0123.jpg」がそのまま使用されていますが、これでは検索エンジンに画像の内容を伝えることができません。
SEOに効果的なファイル名の付け方
ファイル名は、画像の内容を表す具体的な英単語を組み合わせて作成します日本語ではなく英語を使用し、単語間はハイフン(-)で区切ることが推奨されています。
例えば、SEO対策に関する解説図の場合、「seo-strategy-diagram.jpg」のように、内容を表現する英単語を組み合わせます。アンダースコア(_)ではなくハイフン(-)を使用する理由は、検索エンジンがハイフンを単語の区切りとして認識するためです。
キーワードを含むファイル名の作成
ターゲットキーワードをファイル名に含めることで、そのキーワードに対する関連性を検索エンジンに示すことができます。ただし、キーワードの詰め込みは避け、自然で意味のあるファイル名を心がけます。
「画像SEO」をターゲットキーワードとする場合、「image-seo-optimization-tips.jpg」のように、関連する単語も組み合わせてより具体的なファイル名を作成します。
| 画像内容 | 良いファイル名例 | 悪いファイル名例 |
|---|---|---|
| スマートフォンの画面 | smartphone-screen-ui.jpg | IMG_001.jpg |
| グラフと分析データ | analytics-data-chart.jpg | graph.jpg |
| チームミーティング風景 | business-team-meeting.jpg | DSC_0456.jpg |
ファイル名設定時の注意事項
ファイル名には、日本語や特殊文字の使用を避けることが重要です。これらの文字はURL上で文字化けを起こす可能性があり、検索エンジンの認識を妨げる要因となります。
また、ファイル名は短すぎず長すぎない、適度な長さに調整することが大切です一般的には3〜5単語程度で構成し、内容を的確に表現できる範囲に留めます。

ファイル名も検索エンジンにとって重要な情報源になるので、意味のある名前を付けることが大切です。
バクヤスAI 記事代行では、高品質な記事を圧倒的なコストパフォーマンスでご提供!
バクヤスAI 記事代行では、SEOの専門知識と豊富な実績を持つ専任担当者が、キーワード選定からAIを活用した記事作成、人の目による品質チェック、効果測定までワンストップでご支援いたします。
ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

サービス導入事例

株式会社ヤマダデンキ 様
生成AIの活用により、以前よりも幅広いキーワードで、迅速にコンテンツ作成をすることが可能になりました。
親身になって相談に乗ってくれるTechSuiteさんにより、とても助かっております。
▶バクヤスAI 記事代行導入事例を見る

画像のファイルサイズと形式の最適化
画像のファイルサイズと形式の最適化は、ページの読み込み速度向上とSEO効果の両方に直接影響する重要な要素です。
適切な最適化により、ユーザーエクスペリエンスの向上と検索エンジンの評価向上を同時に実現できます。特に、モバイルユーザーにとって読み込み速度は重要な要因となるため、画像最適化の重要性は高まっています。
適切な画像形式の選択方法
画像の内容や用途に応じて、最適な形式を選択することが重要ですJPEG、PNG、WebPなど、それぞれの形式には特徴があり、適切な使い分けが必要です。
写真や複雑なグラデーションを含む画像にはJPEG、透明背景が必要な画像やシンプルなイラストにはPNG、次世代形式として注目されているWebPは、従来の形式よりも高い圧縮率を実現できます。
| 画像形式 | 適用場面 | 特徴 |
|---|---|---|
| JPEG | 写真、複雑な画像 | 高圧縮率、透明背景不可 |
| PNG | ロゴ、透明背景必要 | 可逆圧縮、透明背景対応 |
| WebP | すべての用途 | 高圧縮率、次世代形式 |
| SVG | アイコン、ベクター画像 | 拡大縮小で劣化なし |
ファイルサイズの圧縮テクニック
画像の品質を保ちながらファイルサイズを削減するには、適切な圧縮設定が必要です。JPEGの場合、品質設定を70〜80%に調整することで、視覚的な品質を保ちながらファイルサイズを大幅に削減できます。
オンライン画像圧縮ツールや画像編集ソフトを活用して、用途に応じた最適な圧縮レベルを見つけることが重要です。一般的には、ウェブ用途では100KB以下を目標とすることが推奨されています
レスポンシブ対応と画像サイズの設定
様々なデバイスサイズに対応するため、レスポンシブ画像の実装が重要です。srcset属性を使用して、デバイスの画面サイズに応じた適切なサイズの画像を配信することで、読み込み時間の短縮が可能です。
また、HTMLやCSSで画像のwidthとheightを指定することで、レイアウトシフトを防ぎ、Core Web Vitalsの改善にも寄与します。これらの技術的な最適化は、ユーザーエクスペリエンスとSEO効果の向上に直結します。
画像最適化の実践チェックリスト
- 用途に応じた適切な画像形式を選択している
- ファイルサイズが100KB以下に圧縮されている
- 画像の品質が用途に適している
- レスポンシブ対応の設定を行っている
- widthとheightの指定でレイアウトシフトを防いでいる

構造化データとサイトマップの活用
構造化データと画像サイトマップの実装は、検索エンジンに画像の存在と詳細情報を効率的に伝える高度な画像SEO手法です。
これらの技術的な施策により、通常のクロールでは発見されにくい画像も含めて、検索エンジンに適切にインデックスしてもらうことが可能になります。
画像用構造化データの実装方法
構造化データを使用することで、画像の詳細情報を検索エンジンに構造的に伝えることができます特に、商品画像やレシピ画像、記事のメイン画像などでは、schema.orgの構造化データを活用することが効果的です。
JSON-LD形式で実装する場合、ImageObjectスキーマを使用して、画像のURL、説明、著作者、ライセンス情報などを詳細に記述できます。これにより、リッチリザルトでの表示機会の向上も期待できます。
画像サイトマップの作成と送信
画像サイトマップは、ウェブサイト内のすべての重要な画像を検索エンジンに効率的に伝える仕組みです。XMLサイトマップに画像情報を含めることで、通常のクロールでは見つからない画像も確実にインデックスしてもらえます。
画像サイトマップには、画像のURL、キャプション、タイトル、ライセンス情報、地理的位置情報などを含めることができ、検索エンジンの理解度向上に寄与します。
| サイトマップ要素 | 記述内容 | SEO効果 |
|---|---|---|
| image:loc | 画像のURL | インデックス促進 |
| image:caption | 画像の説明 | 内容理解の向上 |
| image:title | 画像のタイトル | 関連性の向上 |
| image:license | ライセンス情報 | 信頼性の向上 |
Google Search Consoleでの画像パフォーマンス監視
Google Search Consoleの「画像」レポートを活用することで、画像SEO対策の効果を定量的に測定できます。どの画像がどのキーワードで表示されているか、クリック数やインプレッション数の推移を確認できます。
これらのデータを基に、さらなる最適化ポイントを発見し、継続的な改善を行うことが重要ですまた、エラーレポートを確認して、インデックスに問題のある画像を特定し、対処することも可能です。

構造化データとサイトマップの活用で、検索エンジンとのコミュニケーションがより効果的になりますよ!
よくある質問
画像SEO対策について、よくお寄せいただく質問とその回答をまとめました。これらの疑問を解消することで、より効果的な画像最適化を実践できます。
- alt属性は必ず設定する必要がありますか?
-
コンテンツの理解に関わる画像については、alt属性の設定が推奨されています。ただし、装飾的な画像や背景画像などは空のalt属性(alt=””)を設定することで、スクリーンリーダーの読み上げを防げます。画像の目的に応じて適切に使い分けることが大切です。
- 画像のファイルサイズはどの程度まで圧縮できますか?
-
一般的には、ウェブ用途では100KB以下を目標とすることが推奨されています。ただし、画像の用途や品質要件に応じて調整が必要です。JPEGの場合は品質設定70〜80%、PNGの場合は色数を制限するなど、視覚的な品質を保ちながら最適化することが重要です。
- WebP形式は必ず使用すべきでしょうか?
-
WebP形式は優れた圧縮性能を持つ次世代画像形式ですが、すべてのブラウザで完全にサポートされているわけではありません。picture要素やsource要素を使ってフォールバック対応を行うか、サーバー側での自動変換機能を活用することで、安全にWebPを導入できます。
- 画像SEO効果が現れるまでにどの程度の期間が必要ですか?
-
画像SEO対策の効果は、通常2〜3ヶ月程度で現れ始めることが多いです。ただし、サイトの権威性、競合状況、画像の質やユニーク性などの要因により大きく変動します。継続的な改善と長期的な視点での取り組みが重要です。
これらの質問と回答を参考に、自社の状況に応じた画像SEO戦略を構築してください。
まとめ
画像SEO対策は、検索エンジンでの上位表示とユーザーエクスペリエンス向上を同時に実現する重要な施策です。適切なalt属性の設定、意味のあるファイル名の付与、最適な画像形式とファイルサイズの選択など、基本的な要素から確実に実践することが成功への近道となります。
構造化データや画像サイトマップの活用により、さらに高度な最適化も可能です。これらの施策は単発で終わらせるのではなく、定期的な見直しと改善を継続することで、長期的な効果を期待できます。本記事で紹介した7つのテクニックを実践して、あなたのウェブサイトの画像SEO対策を強化していきましょう。